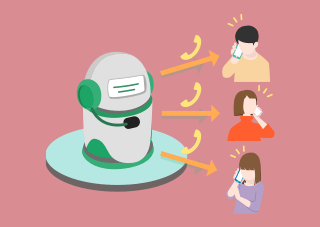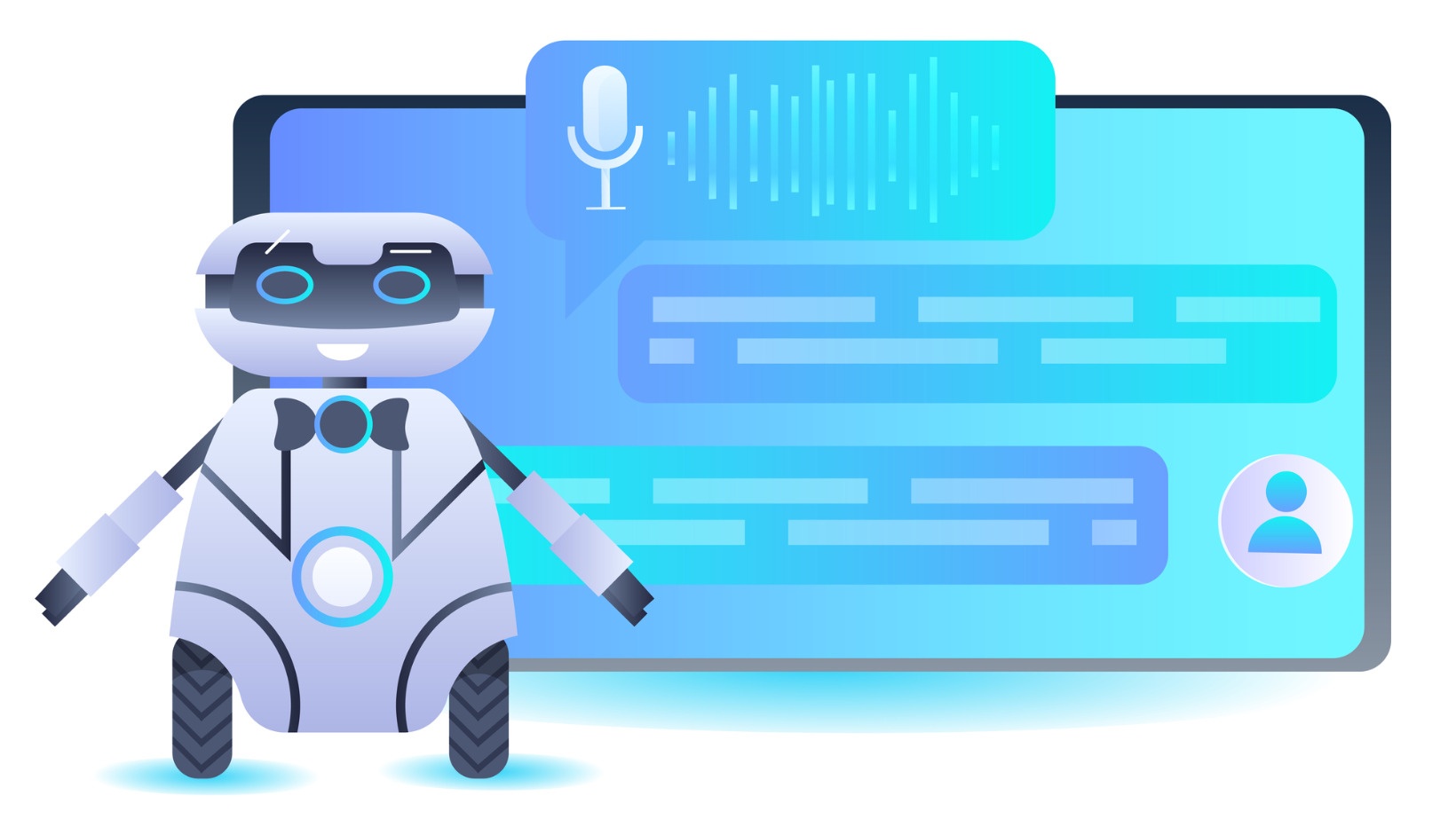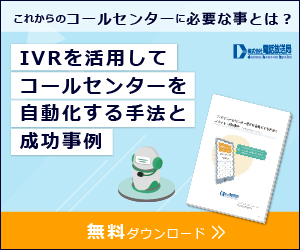AIボイスボットと従来型の違いは?特徴と導入前に知りたい3つの課題
2025/10/29

コールセンター(コンタクトセンター)の現場では、業務効率化や応対品質の向上のため、AIボイスボットの導入が注目されています。
しかし、AIボイスボットといっても、種類によってはその仕組みや得意分野に違いがあります。そのため、従来の「シナリオ型ボイスボット」と、新たに登場した「AIエージェント型ボイスボット」の違いを正しく理解することが、導入成功の鍵といえるでしょう。
そこで本記事では、AIエージェント型とシナリオ型(従来型)ボイスボットの違いを、「柔軟性」と「制御性」という二つの観点から解説します。さらに、AIエージェント型ボイスボットの導入前に知っておきたい課題についても触れますので、自社の電話応対業務に合ったシステムを選ぶための参考にしてください。
なお、「ボイスボットとは何か?」という基本的な仕組みや導入メリットをより深く知りたい方は、まずはこちらの記事をご覧ください。
【関連記事】
ボイスボットとは?メリット・デメリットや活用方法、選定ポイント
目次
・AIエージェント型とシナリオ型(従来型)ボイスボットの違いとは?
・なぜ今、AIエージェント型ボイスボットが注目されているのか?
・AIエージェント型ボイスボット導入前に知っておきたい3つの課題
・AI時代にあえて注目される「シナリオ型ボイスボット」の強み
・【シーン別】AIエージェント型とシナリオ型(従来型)ボイスボットの使い分け
・シナリオ型の安定性×柔軟な対話設計「DHK CANVAS」
AIエージェント型とシナリオ型(従来型)ボイスボットの違いとは?
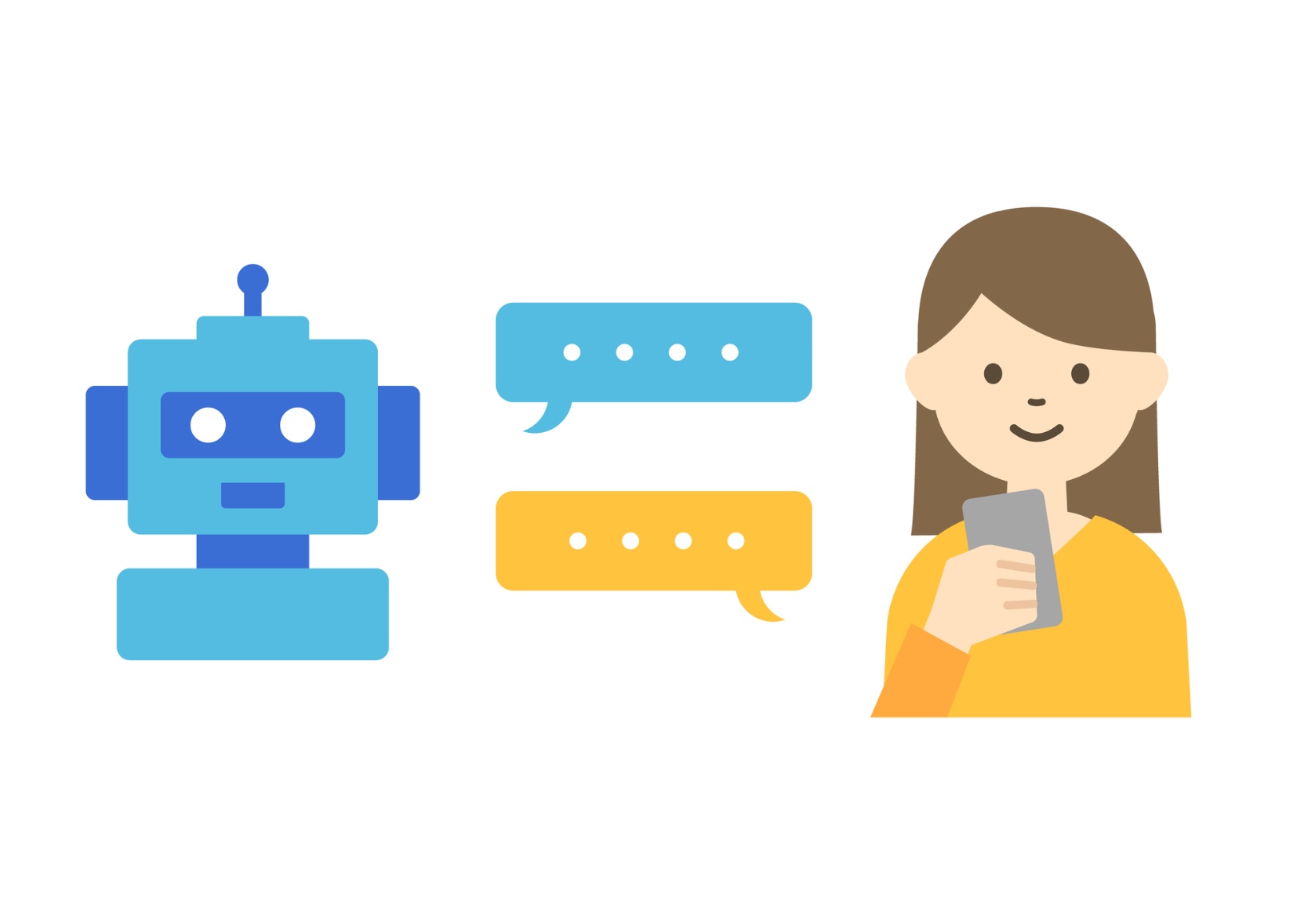
AIエージェント型ボイスボットとシナリオ型ボイスボットの大きな違いは、応答内容を決定する「対話制御」の仕組みにあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
シナリオ型(従来型)ボイスボット
シナリオ型ボイスボットは、あらかじめ設定されたシナリオ(台本)に沿って動作する仕組みです。従来の自動音声応答(IVR)のように「Aの用件は1番」「Bの用件は2番」といったルールに基づいて分岐しながら対話を進めます。
この方式は、設計した通りの結果を出力するため、応答の一貫性や確実性に優れています。定型的な受電業務を安定して処理できる点が強みであり、入電理由が明確な業務において高い「制御性」を発揮します。一方で、想定外の質問やシナリオ外の発話には対応しづらいです。
AIエージェント型(生成AI活用型)ボイスボット
AIエージェント型ボイスボットは、AIが顧客の発話内容を解析し、その背景にある「意図(インテント)」を理解して出力する仕組みです。機械学習を活用しているため、顧客の自由な話し方や曖昧な表現にも柔軟に対応できる点が特徴です。
決められたシナリオに依存せず、AIが発話内容をリアルタイムで理解し、回答を生成することで、自然な対話に近づけられます。こうした高い「柔軟性」を持つため、従来のボイスボットでは対応が難しかった複雑な問い合わせにもスムーズに応答できるようになりました。
なぜ今、AIエージェント型ボイスボットが注目されているのか?
AIエージェント型ボイスボットが注目を集める背景には、生成AIによる言語理解と音声認識技術の進化があります。
従来の自動応答システムでは、あらかじめ決められた選択肢に沿ったやり取りしかできませんでした。
しかしAIエージェント型では、顧客の発話内容や意図をAIが文脈から理解し、状況に応じて適切な応答を生成できます。
これにより、顧客はプッシュ操作や決まった言葉に縛られず、自然な会話の流れで用件を伝えられるようになりました。
応対体験の向上はもちろん、オペレーターの負担軽減や業務効率化にもつながる点が、AIエージェント型が注目されている理由といえるでしょう。
AIエージェント型ボイスボット導入前に知っておきたい3つの課題

AIエージェント型の柔軟性は魅力的ですが、導入前には注意が必要な点もあります。
ここでは、押さえておきたい3つの課題を紹介します。
【課題1】応答品質のコントロールと誤認識のリスク
AIエージェント型は、AIが自ら応答を生成する仕組みを持つため、事実と異なる内容を出力してしまう「ハルシネーション」のリスクを伴います。
また、学習データに含まれていない専門用語や想定外の質問に対しては、曖昧な回答や誤案内をしてしまうケースもあります。
特に、正確性が重視される業務では、AIの応答をそのまま顧客に提供することが難しい場面もあるでしょう。運用時には、応答品質を一定に保つためのガイドライン設計や、人によるモニタリング体制の整備が欠かせません。
【課題2】コストと専門知識を要する運用体制
AIエージェント型の多くは、API(外部AI機能を呼び出す仕組み)の利用量に応じた「従量課金制」を採用しています。
そのため、問い合わせ件数の増減によって費用が大きく変動する場合があり、運用コストの予測が難しい点が課題です。
さらに、AIの応答精度を維持・向上させるには、定期的な学習データの整備やチューニング作業が不可欠です。こうした作業を行うには専門的な知識を持つ人材が求められるケースも多く、社内リソースだけでの対応が難しい場合には、外部の支援を検討することも重要です。
【課題3】セキュリティとガバナンスの懸念
外部のAIサービスを利用する場合、顧客との通話データや個人情報などが外部システムに送信されることになります。
このため、企業のセキュリティポリシーや個人情報保護法、さらには業界ごとのガイドラインに適合しているかを慎重に確認する必要があります。
特にCRM(顧客管理システム)や社内データベースと連携させる場合には、情報の扱い方やアクセス権限の設定など、ガバナンス面での検討も欠かせません。監査対応を見据えたデータ管理体制を構築しておくことが、信頼性確保の鍵となります。
AI時代にあえて注目される「シナリオ型ボイスボット」の強み

AIエージェント型の課題が認識されるなかで、これまで主流だった「シナリオ型(従来型)ボイスボット」の価値が改めて見直されています。
【強み1】応答品質をコントロールできる安定性(制御性)
シナリオ型ボイスボットの特徴は、設計したシナリオ通りに正確に動作する「制御性」にあります。AIエージェント型のようなハルシネーション(誤応答)のリスクがなく、常に一定の品質で運用できる点が強みです。
そのため、金融・医療・公共サービス・インフラなど、高い安定性と正確性が求められる業界やサービスでの活用にも向いています。
【強み2】明確なコスト体系と導入のしやすさ
多くのシナリオ型ボイスボットは、月額固定料金などの明確な料金体系を採用しており、運用コストの見通しが立てやすい点が魅力です。
さらに、近年はノーコードでシナリオ作成・修正できる製品も増え、現場主体で運用開始しやすくなりました。
【強み3】堅牢なセキュリティとガバナンス
一般的にシナリオ型ボイスボットは、対話データを外部のAIプラットフォームへ送信せず、自社システム内で完結して処理する構造です。
この仕組みにより、情報漏えいのリスクを抑えながら安全にデータを管理できます。そのため、企業の厳格なセキュリティ基準や監査要件にも対応しやすく、個人情報を扱う業務でも安心して導入できる点が評価されています。
【シーン別】AIエージェント型とシナリオ型(従来型)ボイスボットの使い分け

AIエージェント型とシナリオ型ボイスボットは、どちらが優れているというものではありません。
それぞれが持つ「柔軟性」と「制御性」の特性を理解し、業務目的に応じて使い分けることが重要です。これは電話のボイスボットだけでなく、チャットボットにも共通する考え方です。
| 利用シーン | 向いているタイプ | 理由 |
|---|---|---|
| 定型業務 (予約受付、資料請求、支払い案内) |
シナリオ型 (従来型) |
安定性・処理速度を重視し、誤案内が許されないため(制御性) |
| 複雑な問い合わせ (FAQ対応、製品相談) |
AIエージェント型 | 顧客の意図を汲み取り、柔軟な応答が求められるため(柔軟性) |
| 厳格な業務 (金融、医療、行政、インフラ) |
シナリオ型 (従来型) |
品質保証とガバナンス対応が必須のため(制御性) |
| CX重視の領域 (顧客満足度やブランド体験) |
AIエージェント型 | 自然な会話体験がブランド価値を高めるため(柔軟性) |
【関連記事】
チャットボットの種類と特徴|メリット・デメリットと業界別の選び方
現場のニーズに応える高機能ボイスボット3選

ここでは、実際にさまざまな業界で導入され、現場の課題解決に貢献しているボイスボットサービスを紹介します。
シナリオ型の安定性×柔軟な対話設計「DHK CANVAS」
シナリオ型の「制御性」を基盤に、AIエージェント型の柔軟な対話設計をノーコードで実現する機能を、2026年春頃にリリース予定です。
シンプルなIVRから複雑な分岐処理まで、現場の要件に合わせて迅速に構築でき、スピーディな業務改善を可能にします。
DHK CANVAS
発信業務を効率化する「オートコールIVR」
督促連絡・アンケート調査・キャンペーン告知など、大量の架電業務を自動化するアウトバウンド特化型のサービスです。
発信業務の効率化により、オペレーターの負担軽減と稼働コストの削減を実現します。
オートコールIVR
代表電話の一次対応を自動化する「とりつぎ君」
企業の代表電話にかかってくる担当者への取り次ぎ依頼を自動化するサービスです。発話した内容や用件に基づき、適切な部署や担当者へ自動で振り分けます。総務・管理部門の電話対応工数を大幅に削減できるのが特徴です。
とりつぎ君
AIボイスボット時代に求められる「ちょうどいい」選択とは
本記事では、AIエージェント型ボイスボットとシナリオ型(従来型)ボイスボットの違いと、それぞれの特性を紹介しました。
AIエージェント型は「柔軟性」に優れる一方、コストや応答品質の制御が課題となります。対してシナリオ型は「制御性」に優れながらも、対応範囲が限定されるという特徴があります。
実際のコールセンター業務では、両者の特性をバランス良く活かすことが理想的です。
今後は「柔軟性」と「制御性」を両立させた「ちょうどいいボイスボット」が求められていくでしょう。
電話放送局が提供する「DHK CANVAS」は、シナリオ型の安定性に加え、AIエージェント型の自然な対話体験を組み合わせたソリューションを、2026年春のリリースを目指して開発中です。
多様な導入実績を参考に、自社の目的や課題に対応できるAIボイスボットを選定し、次世代の顧客体験向上へつなげていきましょう。
電話放送局が提供するサービスの導入事例はこちらから
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、ボイスボット・IVRを活用したコールセンター業務を自動化する際の手順を知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・自動化に適したコール内容を知りたい
・ボイスボット・IVRを導入することが決まり、サービス選考段階
・自動化する業務の選定や、導入する際の考え方や手順を整理したい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(3)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711