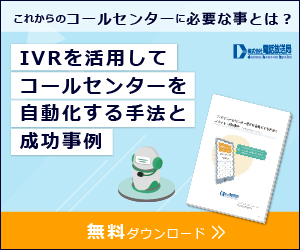CX(顧客体験)やEX(従業員体験)の意味とは?関係性や向上させるメリット
2025/03/06

企業の競争力強化を実現するには、「CX(顧客体験)」と「EX(従業員体験)」を向上させることが重要です。特に、コールセンターをはじめとしたカスタマーサポートの現場では、CXとEXを同時に高める施策により、大幅な業務改善の効果が見込めます。
この記事では、「CX(顧客体験)」と「EX(従業員体験)」に関する基礎知識や、両者の関係性、向上させるメリットについて解説します。CX・EXの改善へ向けて、ぜひ参考にお読みください。
目次
・コールセンターのCX・EX改善にはボイスボットとIVRがおすすめ
CX(顧客体験)とは

初めに、「CX(顧客体験)」に関する基礎知識を解説します。自社の商品・サービスの顧客満足度向上へ向けて、CXの基本を改めて確認してみましょう。
CXの意味
CXとは「Customer Experience」を略した用語です。日本語では「顧客体験」と訳され、顧客が企業やブランドと接する際のあらゆる体験を総称してCXと呼びます。近年は多くの企業がマーケティング施策の一環として顧客体験価値(経験価値)の向上に取り組んでいます。
CXの考え方では、顧客が商品・サービスを認知する段階、購入する段階、購入後に利用する段階まで、顧客視点での一連の体験が対象となります。商品・サービスを利用した体験だけでなく、顧客が店舗を訪れたときの「店員の接客態度」「店内の内装やBGM」「陳列棚のレイアウト」「商品の品揃え」といった全ての体験がCXに含まれます。
CXを向上させるメリット
企業がCXを向上させると、顧客満足度の向上により、リピーターやファンを増やす効果が期待できます。また、顧客によるポジティブな口コミやレビューが活発に行われることで、新規顧客の獲得につながるのもメリットです。さらには、顧客体験価値が高まることで競争優位性を確立できれば、市場で価格競争に巻き込まれにくくなるというメリットもあります。
EX(従業員体験)とは

続いて、「EX(従業員体験)」に関する基礎知識を解説します。従業員満足度の向上は、企業と従業員の双方にメリットをもたらします。自社のEX向上へ向けて、ぜひ参考にしてみてください。
EXの意味
EXとは「Employee Experience」を略した用語です。日本語では「従業員体験」と訳され、従業員が企業で働く際のあらゆる体験を総称してEXと呼びます。近年の少子高齢化にともなう労働力不足などを背景に、多くの企業が人材の確保を目的としてEXの向上に取り組んでいる状況です。
具体的にEXに該当するのは、「業務内容」「業務量」「給与」「研修制度」「オフィスの設備」「福利厚生」「ワークライフバランス」「上司や同僚との人間関係」「顧客との人間関係」などです。また、前述した職場環境や組織文化だけでなく、「仕事の成果を褒められた」「自社のビジョンへ共感した」といった従業員の心理的な体験もEXの対象となります。
EXを向上させるメリット
企業がEXを向上させると、従業員のモチベーションが高まり、離職率の低下につながります。また、働きがいのある会社として自社の魅力が高まることで、優秀な人材の定着が促されるのもメリットです。結果として労働力を確保しやすくなり、企業競争力を向上させる効果が期待できます。従業員側だけでなく、企業側にも多くのメリットがもたらされるでしょう。
CXとEX・DXの関係性とは

ここまでご紹介した「CX(顧客体験)」や「EX(従業員体験)」と似たビジネス用語に、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」があります。ここでは、それぞれの関係性や相互作用について解説します。
CXやEXとDXの関係とは
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは、業務のデジタル化により既存のビジネスモデルを変革し、顧客目線で新たな価値を創出する取り組みのことです。CXやEXを改善する上で、DXは重要な手段となります。デジタル技術の活用により、顧客体験価値を最適化したり、業務効率化を実現したりすることが可能です。DXを推進することでCXやEXが向上すると、企業の競争力強化につながります。
【参考記事】
バックオフィスDXとは?重要性や期待できる効果、導入の流れ
CXとEXの相互作用とは
CXとEXは、相互に影響を与え合う関係にあります。従業員の満足度やエンゲージメントが高い組織では、より良い商品・サービスを提供でき、CXが向上します。その反対に、顧客からの好意的な評価によって従業員のモチベーションが高まると、EXの向上が期待できるでしょう。このように、企業がCXとEXの好循環を促せると理想的です。
CXやEXを高めるには?

企業が「CX(顧客体験)」や「EX(従業員体験)」を高めるには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。最後に、CXやEXの向上へ向けて理解しておきたいポイントを解説します。
CXを高めるポイント
CXを高めるには、顧客目線を重視して、満足度の高い体験を提供する必要があります。そのためにも、データを分析して顧客に適した商品・サービスを提案したり、サポート体制を強化したりする施策が有効です。その際は、「NPS®(ネットプロモータースコア)」などのアンケート調査を実施し、顧客ロイヤルティを可視化することで、現状の課題を明らかにできます。
【参考記事】
NPS®とは?顧客ロイヤルティの評価に活用するメリット、調査方法
EXを高めるポイント
EXを高めるには、従業員が働きやすい職場環境を整備し、モチベーションを高めることが大切です。具体的には、柔軟な働き方を推進したり、社内コミュニケーションを活性化したり、キャリア形成を支援したりする施策が有効だといえます。その際は、「エンゲージメントサーベイ」などの社内調査を実施し、従業員の会社に対する愛着や課題を把握すると良いでしょう。
CXとEXを同時に高めるためのポイント
CXとEXを同時に高めるには、基本的にはEXを優先するのが望ましいとされます。まず従業員の満足度を高めた上で、CXの向上を図ると良いでしょう。改善の施策では、デジタルツールの活用によって業務効率化とサービス品質向上を同時に実現できる可能性があります。また、近年は顧客と従業員によるコミュニティ活動で、相互理解や共感を生む施策も注目されています。EXとCXの相互作用に着目して改善を目指しましょう。
コールセンターのCX・EX改善にはボイスボットとIVRがおすすめ
ここまで、「CX(顧客体験)」と「EX(従業員体験)」に関する基礎知識や、両者の関係性、向上させるメリットについて解説しました。CXとEXは相互に影響を与え合う関係にあります。顧客や従業員の現状を把握し、自社の課題に応じた改善の施策を検討しましょう。
CXとEXを同時に高めるには、業務の自動化が欠かせません。サービス品質を改善して顧客満足度を高めながら、現場の業務負担を軽減することで、企業全体のCXとEXを改善することが可能です。なかでもコールセンター業務は、業務の自動化によってCXとEXの双方を向上しやすいといえます。CX・EXを改善するソリューションをお探しのご担当者様は、電話放送局へお問い合わせください。
電話放送局が提供する「ボイスボット」や「IVR(自動音声応答サービス)」は、顧客満足度向上と業務効率化を同時に実現できるのが特長です。例えば、対話型IVRで受電業務を自動化するサービスや、SMS送信で顧客案内を自動化するサービスなど、多彩なラインナップをご用意しています。デジタルツールの活用でコールセンター全体の業務を自動化・半自動化できるのが強みです。
コールセンター業務を自動化する具体的な手順については、以下のページからダウンロードしていただける無料の資料で詳しく解説しています。コールセンターの業務改善でお悩みのご担当者様は、どうぞお気軽にお申し込みください。
DHK CANVAS
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、ボイスボット・IVRを活用したコールセンター業務を自動化する際の手順を知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・自動化に適したコール内容を知りたい
・ボイスボット・IVRを導入することが決まり、サービス選考段階
・自動化する業務の選定や、導入する際の考え方や手順を整理したい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(4)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAQ(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711