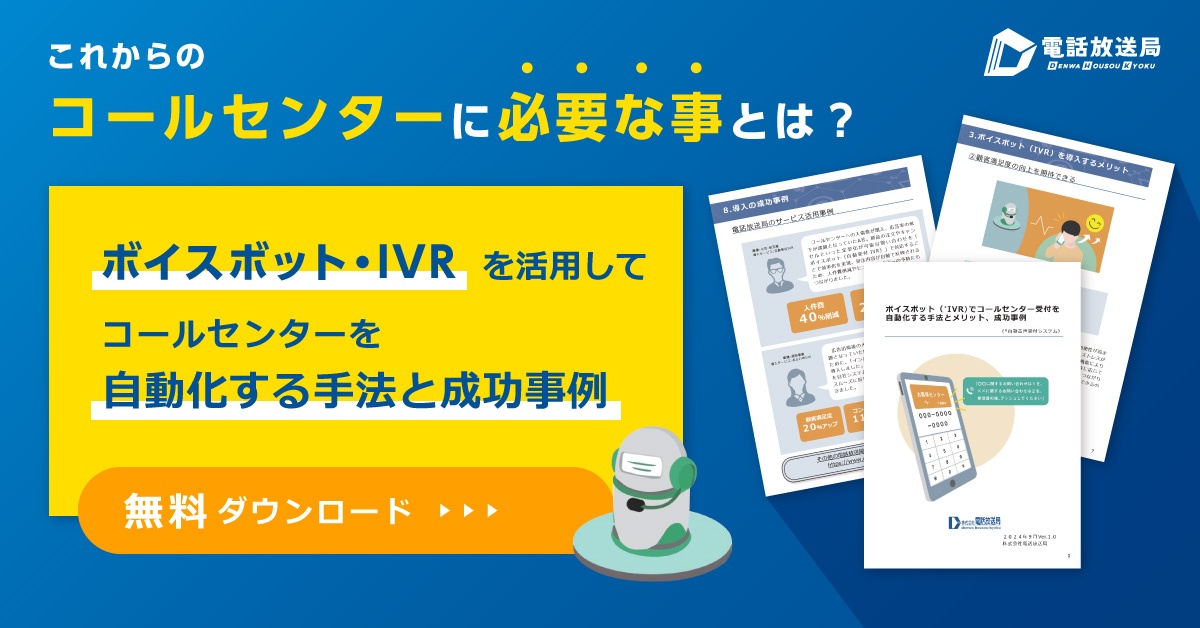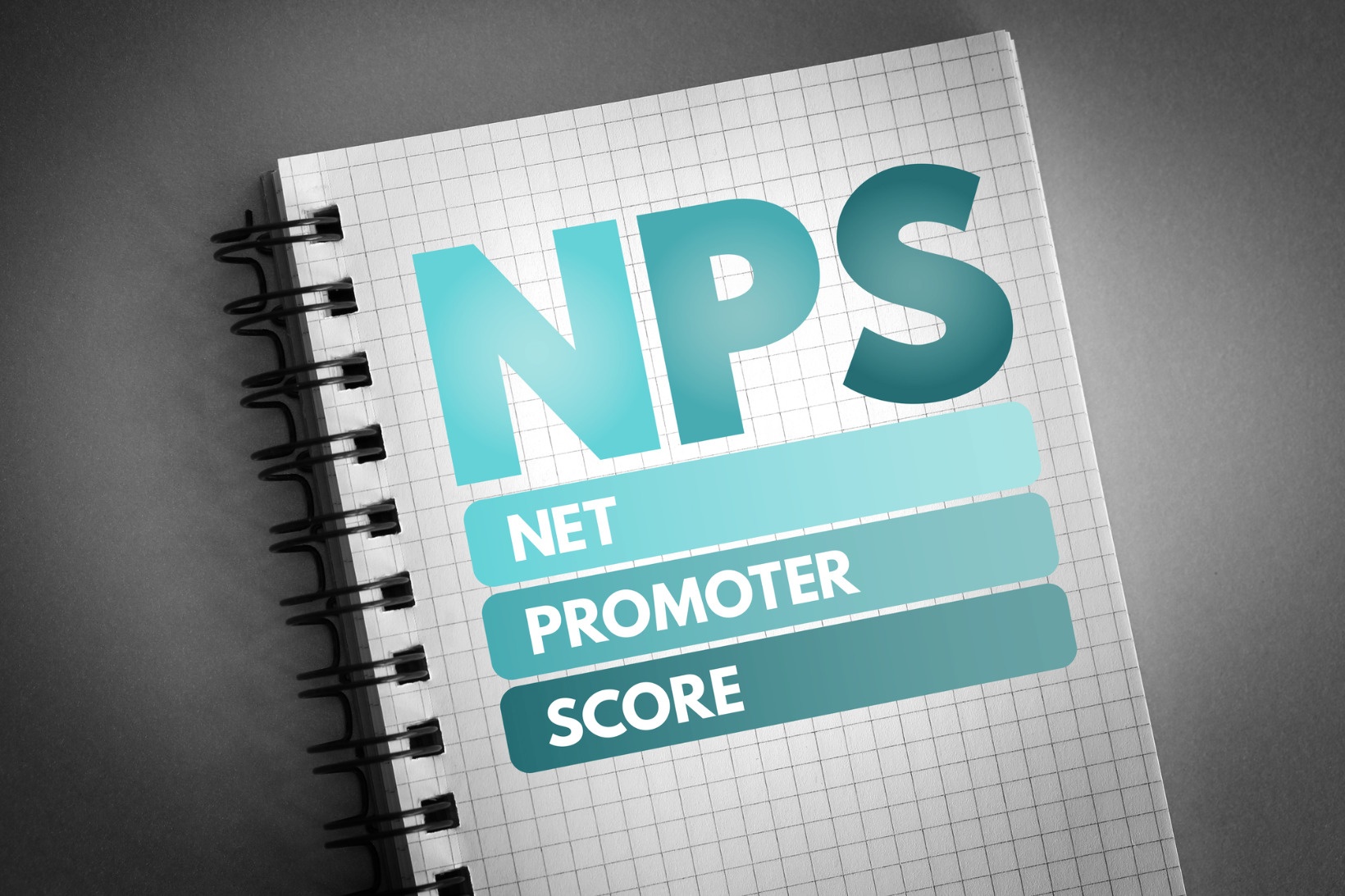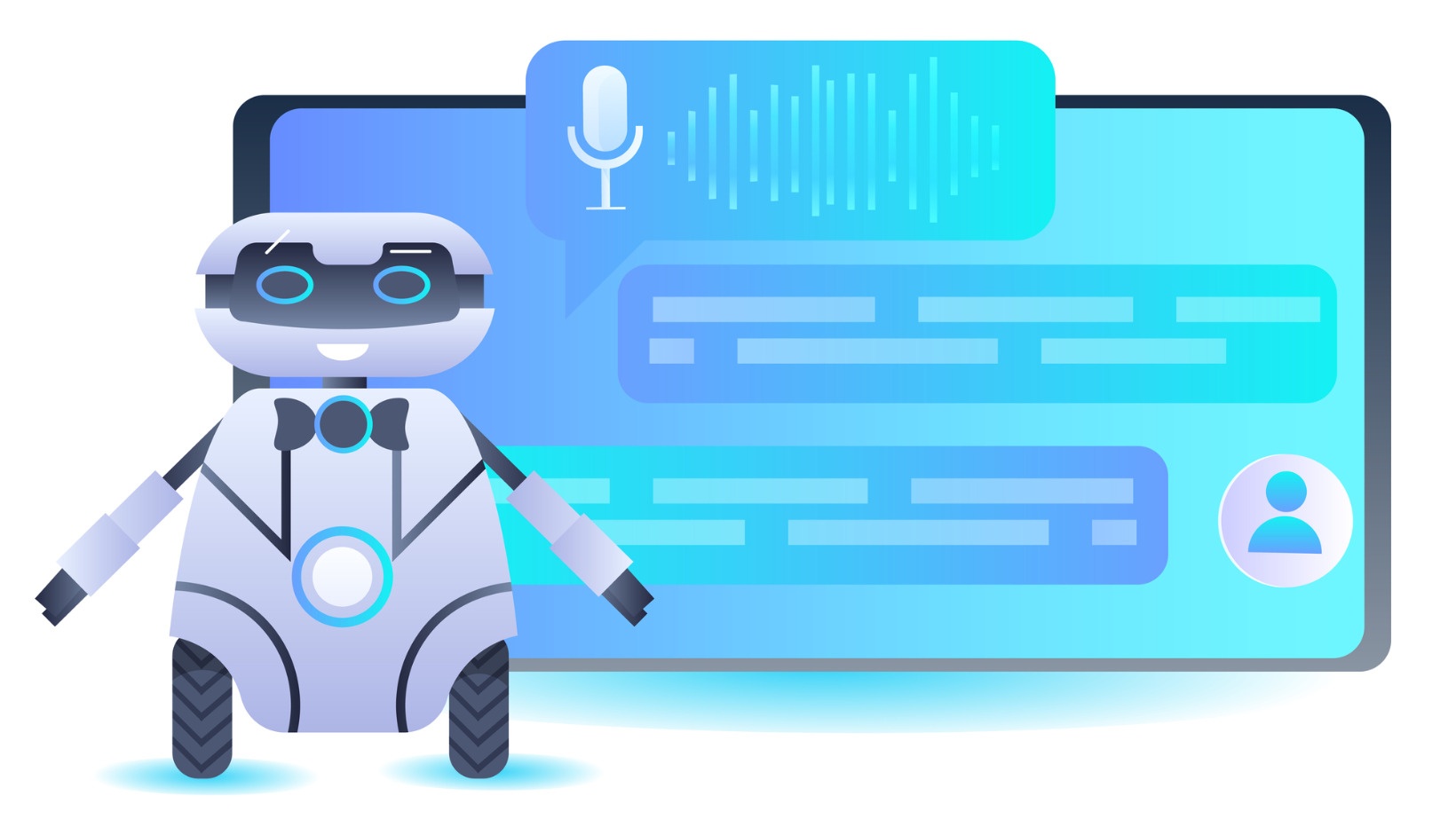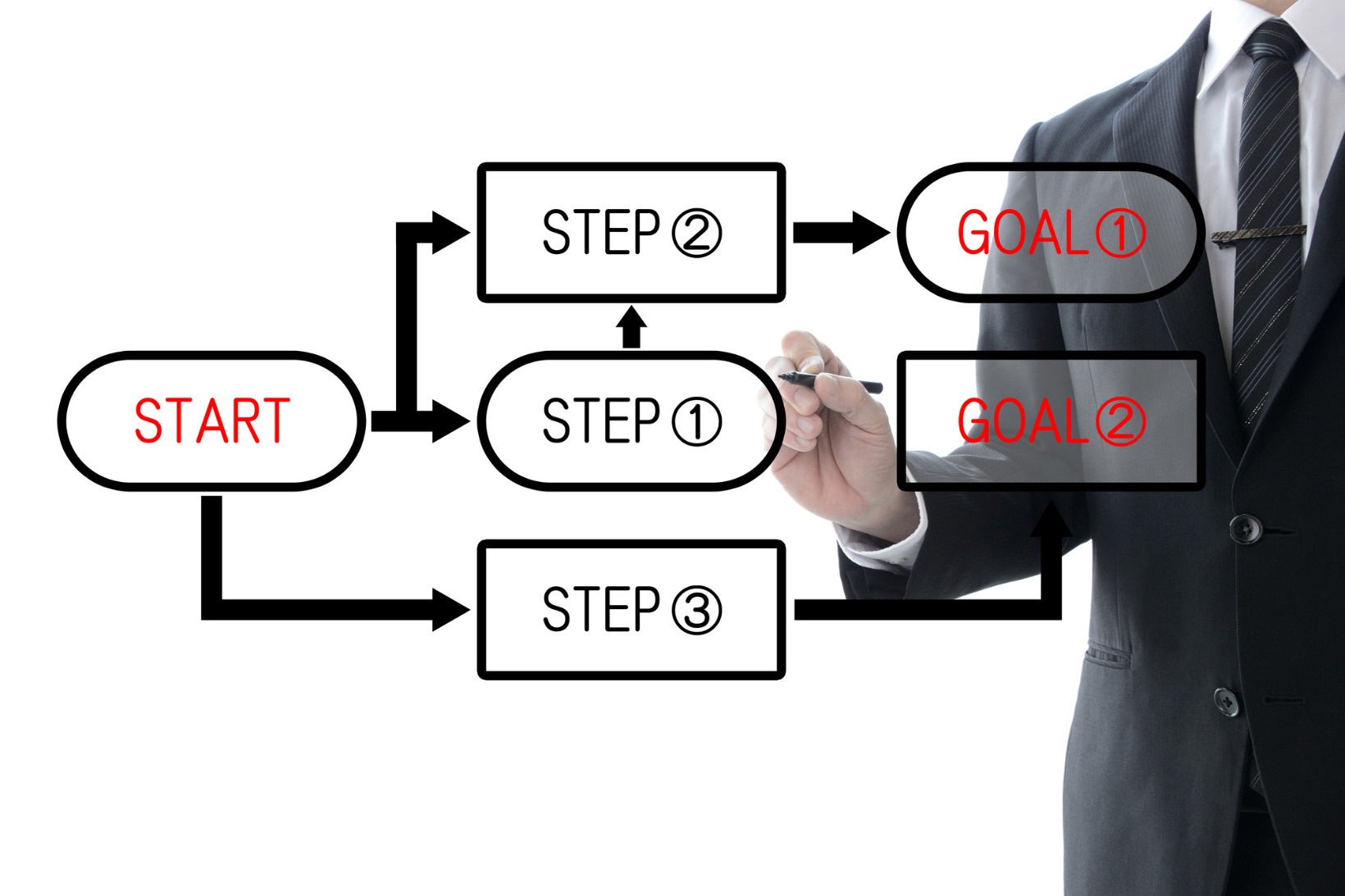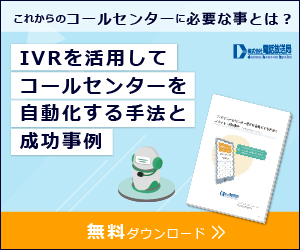顧客満足度調査とは?実施する目的や調査の流れ、代表的な調査方法
2025/10/24

自社の商品・サービスをより良いものにするには、ユーザーの声が欠かせません。コールセンターの応対品質を向上させるには、顧客からの評価へ目を向け、自社の現状を把握することから始めましょう。
ここでは、企業の商品やサービスへの満足度を知るために役立つ、「顧客満足度調査」について解説します。調査を実施する際のポイントや、実施手段もご紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。顧客満足度を向上させ、さらにユーザーから選ばれるブランドを目指しましょう。
目次
顧客満足度調査とは?
顧客満足度調査とは、自社が提供する商品やサービス、顧客対応などに対して、顧客がどの程度満足しているかを測定・分析するための調査活動です。主にアンケートなどを通じて、顧客の意見を定量・定性の両面から収集・分析します。その結果を、事業活動の改善や次の戦略立案に活かすことが目的です。
そもそも顧客満足度とは
顧客満足度とは、企業の商品やサービスなどに対して、顧客がどれほど満足しているかを示したものです。満足度の程度には、商品やサービスなどへの期待値が関係しています。顧客の期待値を上回る価値を提供できた場合は、満足度が高まりやすいといえます。その反対に、期待値を下回った場合は満足度が低くなる傾向にあるため、注意が必要です。
なお、顧客満足度とよく似た指標として、「顧客ロイヤルティ」が挙げられます。ロイヤルティ(Loyalty)という言葉には「忠誠心」という意味があり、ブランドに対する信頼や愛着を示したものです。
顧客満足度調査を行う目的
顧客満足度調査は、単に顧客の満足度を測るだけでなく、企業の持続的な成長のために様々な目的をもって実施されます。
・現状把握と改善点の抽出
顧客の声から自社の強み・弱みを把握し、優先して改善すべき点を見つけます。
・利用者の信頼感を高める土台づくり
不満を早期にとらえ対応することで、利用者の離脱を抑え、支持を獲得しやすくなります。
・意思決定の裏付けを得る
体系的に得られたデータをもとに、施策の優先順位や方針を判断できます。
顧客満足度調査の流れ
STEP1.調査の準備
初めに、自社が顧客満足度を調査する目的や、目標を設定します。その後、目的を踏まえた調査内容や、適切な方法などを検討し、調査計画を作成します。
STEP2.調査の実施
準備段階で作成した計画に沿って、ユーザーへの調査を行います。調査の実施後は、分析へ向けて集めたデータを集計しましょう。
STEP3.調査結果の分析
調査結果を分析し、結論を出します。自社の強みや、課題を明らかにすることが大切です。分析によって立てた仮説を基に、顧客満足度を向上させるための施策を検討します。
顧客満足度の主な指標
顧客満足度を測定するためには、目的に応じてさまざまな指標が用いられます。ここでは、代表的な4つの指標について解説します。
CSAT
CSAT(Customer Satisfaction Score)は、商品購入や問い合わせ対応など、特定の体験に対する顧客の満足度を直接的に測る指標です。「とても満足」「満足」「普通」「不満」「とても不満」といった5段階評価などで質問することが多く、顧客の体験直後の満足度をシンプルに測定できるのが特長です。
NPS®
NPS®(Net Promoter Score)は、「この商品を友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」といった質問を通じて、顧客のロイヤルティ(愛着・信頼)を測る指標です。単なる満足度だけでなく、将来の収益につながる「推奨意向」を数値化できるのが特徴です。多くの企業が、NPS®と成長指標との関連性に注目し、顧客ロイヤルティを把握する枠組みとして活用しています。
【関連記事】
NPS®とは?顧客ロイヤルティの評価に活用するメリット、調査方法
CES
CES(Customer Effort Score)は、商品の購入や問題解決の際に、顧客が「どのくらいの労力(手間)を要したか」を測る指標です。「少ない努力で目的を達成できたか」を問うことで、顧客体験のスムーズさを評価します。この指標は、顧客の手間を減らすことが満足度やリピート率の向上につながるという考え方に基づいています。
JCSI
JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)は、サービス産業生産性協議会(SPRING)が公表する日本独自の顧客満足度指標です。「顧客期待」「知覚品質」「知覚価値」「顧客満足」「推奨意向」「ロイヤルティ」という6つの要素を因果モデルで分析し算出します。業界内だけでなく他業種とも比較できるため、自社の立ち位置を客観的に把握するベンチマークとして広く活用されています。
顧客満足度調査を実施する前の準備とは?
顧客満足度調査を実施し、リサーチ結果を改善へ役立てるには、以下のポイントを意識しましょう。ここでは、マーケティングリサーチを十分に活用するために、企業が注意したい点を解説します。
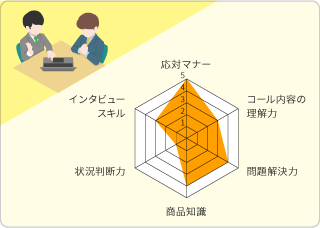 弱点を特定
弱点を特定
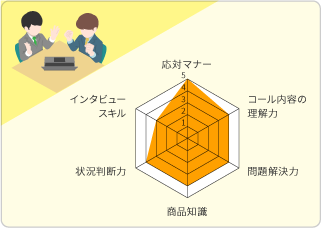 弱点を強化
弱点を強化
調査の目的を整理する
顧客満足度調査を実施すること自体は、本来の目的ではありません。調査の目的は、調査によって得られた情報をもとに、次のアクションを起こすことです。調査後に顧客満足度を向上させるためには、調査を通じてどのような点を明らかにしたいのか、どのような課題を解決したいのかを、事前に整理しておくことが大切です。
顧客に尋ねる内容を決める
顧客満足度調査では、調査の目的に適した質問を用意しておきましょう。目的と無関係な質問では、その後に役立てられる意見や結果は得にくいためです。自社の価値につながる質問のみを集め、必要最低限の設問数に絞り込むよう心がけましょう。その際は、ほかの企業や自治体が実施した調査の質問を参考にしたり、活用したりするのも一つの手です。
実施手段を検討する
顧客満足度の調査方法には、複数の選択肢があります。それぞれの調査方法によって、得られる情報の内容が変わってくることも。自社の目的や明らかにしたいことに応じて、適切な手段を選びましょう。なお、各種実施手段について、詳しくは以下の見出しで取り上げます。
代表的な顧客満足度の調査方法
最後に、代表的な顧客満足度の調査方法をご紹介します。調査手法ごとの特徴や、メリット・デメリットを解説するため、比較してみましょう。顧客満足度向上へ向けて、必要な調査データの入手手段をご検討ください。
対面インタビュー
商品やサービスを利用した顧客と対面し、直接質問する形式です。複数人を同時に調査する「グループインタビュー」を行う方法もあります。
【メリット】
・回答するときの顧客の様子や表情など、言葉以外の情報も得られる。
・回答内容に応じて、その場で質問を深掘りできる。
・質問が複雑な場合でも、インタビュアーがその場で意図を補足できるため、回答者に真意が伝わりやすい。
【デメリット】
・ほかの方法と比べてコストや時間がかかる。
・インタビュアーのスキルによって、回答の質が左右される可能性がある。
・回答者に心理的な負担を与えやすく、本音を引き出しにくい場合がある。
インターネット上での調査
自社のWebサイト上の専用ページや、ネットリサーチ専門の調査会社のアンケートページなどで、アンケート調査を行います。
【メリット】
・多くの回答をスピーディかつ低コストで集めやすい。
・写真や動画などを活用した、視覚的に分かりやすい質問ができる。
・回答結果が自動で集計されるため、分析が容易。
【デメリット】
・インターネットを利用しない層には調査が届かない。
・回答の信頼性の担保が難しい(なりすましや、不誠実な回答などのおそれあり)。
・アンケートの回収率が低くなりやすい。
郵送による調査
顧客の家へはがきなどを郵送し、回答してもらう形式です。多くのユーザーを対象にできる点は、インターネットでの調査と同様です。
【メリット】
・インターネット調査では回答を得にくい高齢者層など、幅広い層を対象にできる。
・回答者は時間や場所を選ばず、自分のペースでじっくり考えながら回答できる。
【デメリット】
・アンケートの発送から回収、結果の集計までに時間がかかる。
・印刷費や郵送費、回答をデータ化する人件費などコストがかかる。
・質問の意図が伝わりにくくても、その場で補足説明ができない。
SMS(ショートメッセージサービス)を活用した調査
顧客の携帯電話にURLを添付したSMSを送信する形式です。主にコールセンターで使われています。URLを開いた顧客を、Web上に設けたアンケートサイトへ誘導し、オンラインで回答してもらうのが特徴です。なかには結果の集計を自動で行えるサービスもあります。
【メリット】
・携帯電話番号さえ分かっていれば、幅広い顧客層にアプローチできる。
・問い合わせ直後など、リアルタイムに近いタイミングで案内を送れる。
【デメリット】
・迷惑メッセージと誤解され、不信感を与える可能性がある。
・送信できる文字数が限られているため、調査の目的や趣旨を伝えにくい。
IVR・ボイスボットによる調査
近年では、従来のオペレーターによる電話調査に代わり、自動音声応答(IVR)やボイスボットを活用した顧客満足度調査が広がっています。IVRはプッシュ操作による回答収集を自動化できるのが特長です。さらにボイスボットは、顧客の発話内容をAIが自動でテキスト化し、サービスによっては要約・傾向分析・集計まで行える機能を備えています。これにより、従来よりも効率的かつ多角的な分析が可能になります。
【メリット】
・24時間365日稼働でき、大規模かつ効率的な調査が可能。
・アウトバウンド型(企業から顧客へ発信する調査)にも対応でき、能動的なアプローチが可能。
・人件費を削減しながら、回答データを即時にマーケティングや改善施策へ活用できる。
【デメリット】
・導入には一定のコストがかかる。
・高齢層や機械的な音声に慣れていない顧客には、操作に戸惑う可能性がある。
・自由回答を正確に解釈するには、AI分析の精度向上が前提となる。
IVRは短時間で大量にデータを回収できる効率性が強みであり、ボイスボットはそこに「発話データの活用」という新しい分析軸を加えた形です。両者を使い分けることで、自社に合った調査体制を構築できます。
コールセンターの顧客満足度調査にはIVRがおすすめ
今回は、顧客満足度調査の基礎知識や、実施する際のポイント、実施手段についてお伝えしました。顧客満足度調査は、電話で実施する方法もあります。特に、コールセンターの対応品質を調査する際は、IVRやボイスボットの活用がおすすめです。
電話放送局では、コールセンターの課題解決につながる多彩なサービスを提供しています。顧客満足度を数値化できる「CS調査IVR」では、オペレーターの対応直後のタイミングで、効率的に調査を実施。ボタン操作による5段階評価やYES/NOでの回答のほか、オプションサービスではフリーコメントの録音も可能です。顧客の本音をリアルタイムで収集し、品質改善に役立てられます。
また、顧客からの着信(インバウンド)だけでなく、企業から能動的に発信する(アウトバウンド)調査にも対応しています。
コールセンターに顧客満足度調査を導入する際は、電話放送局の「CS調査IVR」へのお問い合わせをぜひご検討ください。
CS調査IVR
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、ボイスボット・IVRを活用した電話業務を自動化する手法や、ボイスボット・IVR提供会社を選ぶポイントを知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・コールセンターの電話業務をどこまで自動化できるのか知りたい
・自動化に適したコール内容を知りたい
・ボイスボット、IVR導入により、自動化に成功した事例を知りたい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(3)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711