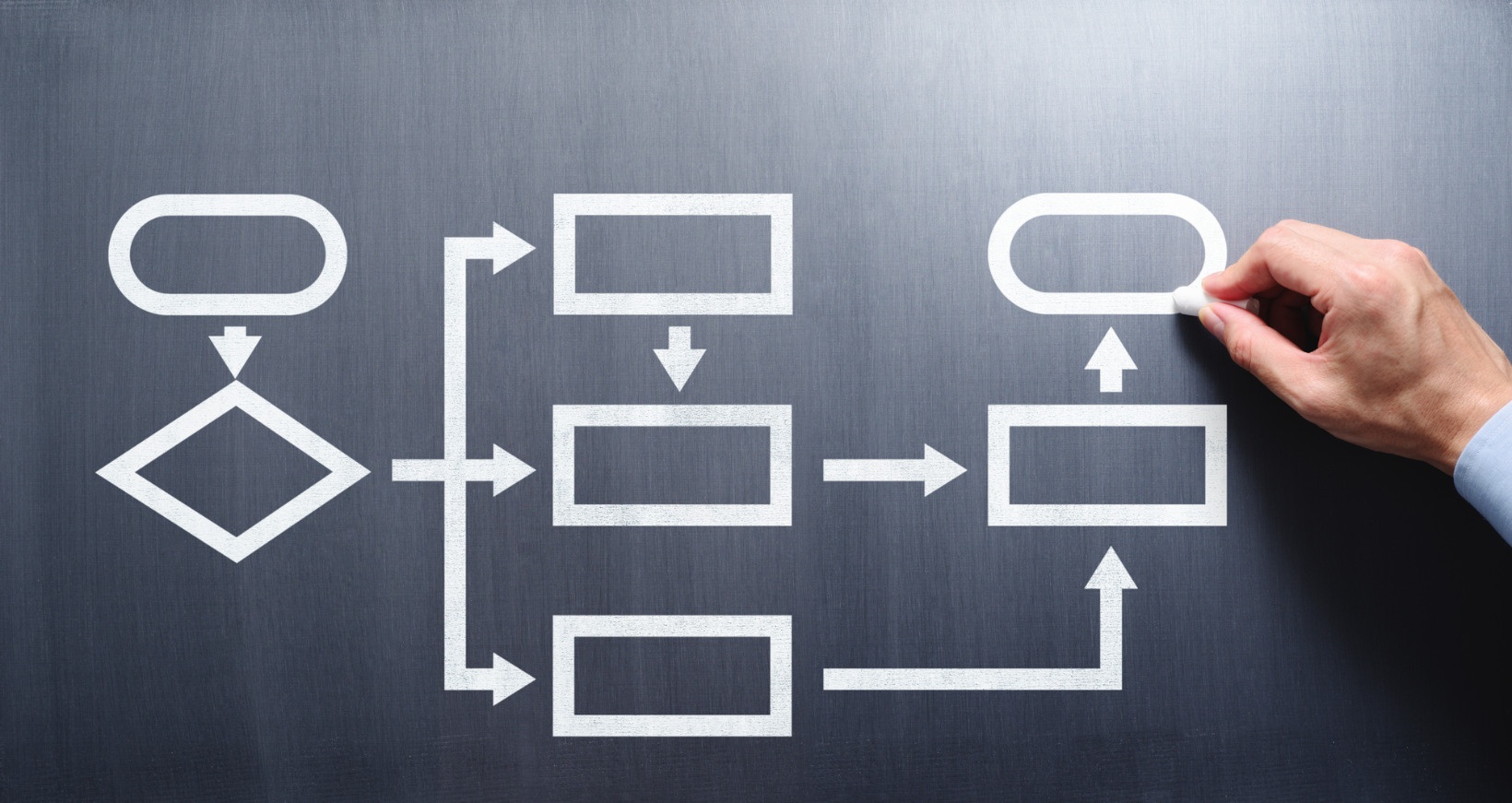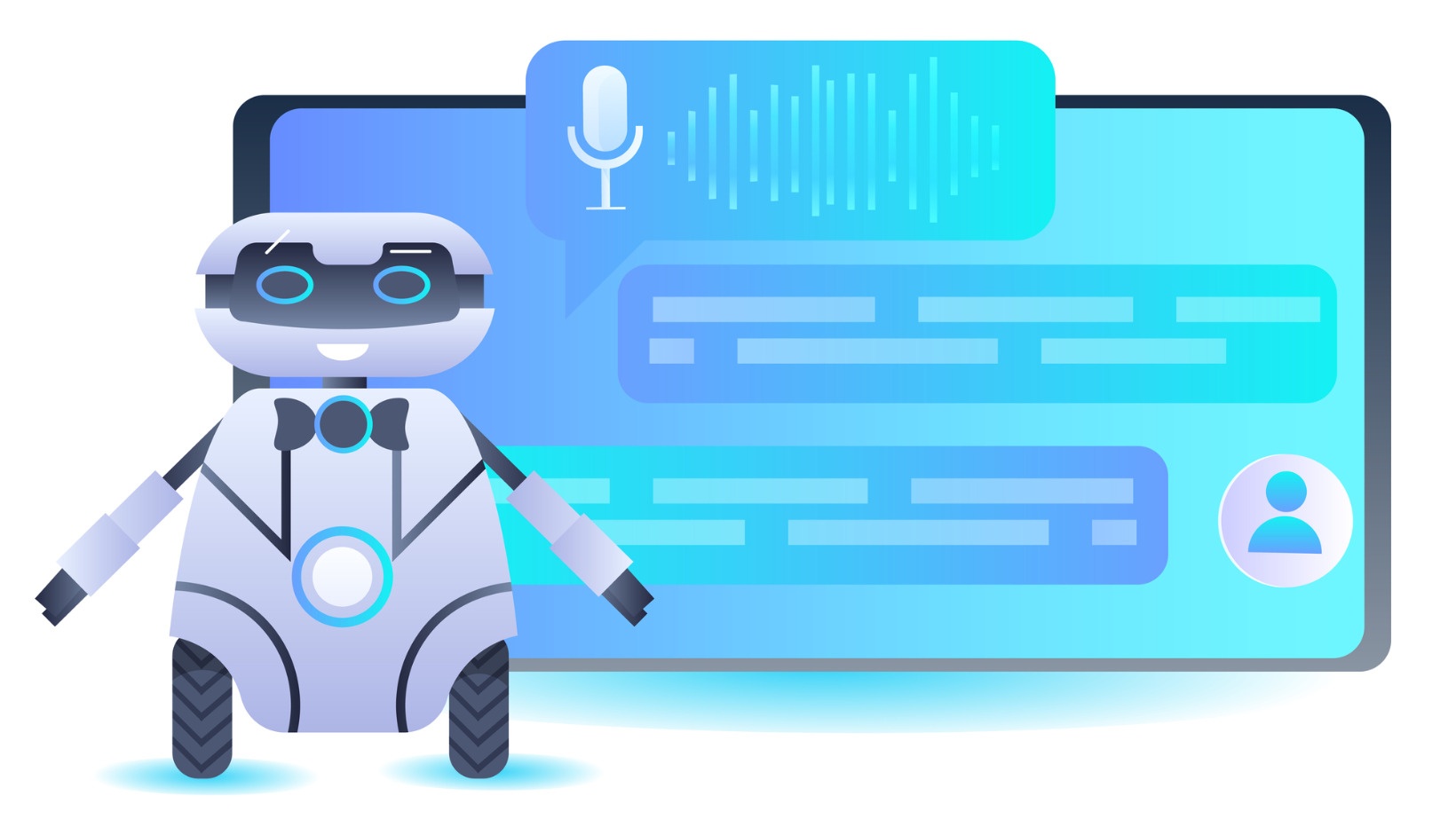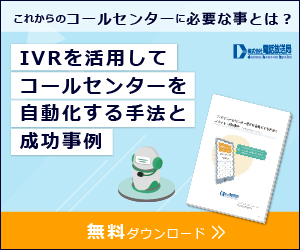自治体DXとは?推進するメリットや進め方|自治体の取り組み事例6選
2025/03/31

デジタル技術が人々の暮らしをより豊かにする昨今、民間企業に限らず、地方自治体でもDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されるようになりました。住民へさらに便利なサービスを提供するためにも、業務効率化を実現するためにも、デジタル活用で価値を創出するDXへの取り組みが求められている状況です。
この記事では、これからの地方自治体が取り組むべき「自治体DX」の基礎知識を、自治体向けにお伝えします。DX推進の目的やメリットのほか、進め方や各自治体の取組状況までご紹介します。自治体や地方公共団体のDX推進に関わるご担当者様は、ぜひご一読ください。
目次
・マイナンバーカードを利用した電子申請・届出システム【岡山県鏡野町】
・オンライン相談ツールの活用による「行かなくて済む区役所」の取組【東京都】
・県と県内市町による高度デジタル人材シェアリング事業【愛媛県】
・デジタル技術を主体的に活用できるDX推進チャレンジャーを育成【滋賀県】
・全59市町村へのICTアドバイザー派遣等にて市町村のDXを底上げ【福島県】
・知事のもとデザイン思考に基づくDXを全庁横断的に推進中【大分県】
自治体DXとは

自治体DXとは、地方自治体が最新のデジタル技術やデータ利活用により、行政サービスや業務プロセスを変革することです。地方自治体のDX推進において目指すべきビジョンは、2020年12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」において示されています。「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」のビジョンのもとで、地方自治体もDX推進に取り組み、地方行政の利便性向上や業務効率化に取り組むことが大切です。
【出典】 「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画【第 2.2 版】」 (総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919590.pdf
自治体DXを推進する目的

自治体DXには、住民の利便性向上や、行政サービスの業務効率化などの目的があります。そこでは、地方自治体の業務にICTを浸透させ、あらゆる側面で生活をより良い方向へ変化させることが目指されています。ICT(Information and Communication Technology)とは、「情報通信技術」を意味する用語です。私たちの身近にあるICTの例として、スマートフォンが挙げられます。今後の地方自治体では、少子高齢化にともなう人口減少が急速に進行すると見込まれているため、地域社会のデジタル化へ向けた基盤の構築が急務です。自治体DXでは、官民連携で新たな価値を創出する取り組みが始まっています。
自治体DXを推進するメリット

自治体DXを推進することで、地方自治体ではどのようなメリットが期待できるのでしょうか。ここでは、行政側・住民側のメリットをそれぞれ解説します。
行政側のメリット
自治体DXによって業務効率化が進むと、行政側では職員の負担軽減が期待できます。また、ペーパーレス化やテレワーク推進などの施策により柔軟な働き方に対応しやすくなるのもメリットです。さらには、新たな価値創出や地域との連携強化を進めやすくなるといったメリットも挙げられるでしょう。ただし、地方自治体は住民が負担する税金によって運営が成立している点に留意する必要があります。税収が増えない地方自治体は、DXを運営する経費が限られていることも少なくありません。
住民側のメリット
自治体DXによって行政サービスが住民のニーズに沿って改革されると、従来よりも住民向けサービスの利便性が高まり利用しやすくなります。また、新たなサービスが創出されることで、地域活性化につながる可能性があるのも大きなメリットです。DX推進によってスマートシティ化や地域ビジネスの振興を実現できれば、市民の生活が豊かになる効果も期待できるでしょう。
自治体DXにおける課題

多くの自治体では、DX推進の機運醸成が進んでいるものの、現場では以下のさまざまな課題が懸念されています。ここでは、自治体DXにおける課題をご紹介します。
デジタル人材の不足
多くの自治体では、デジタル技術に関する専門技術を持ち、DX推進プロジェクトをリードできる人材(=デジタル人材)が不足している傾向にあります。政府は2026年度末までに230万人のデジタル人材育成を目標としているものの、目標値と大きな開きがあるのが現状です。
【参考】「デジタル人材の育成・確保」(内閣官房)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/about/digital-resources.html
根深いアナログ文化
自治体によっては、職員・住民ともに紙の資料や申請書による運用に慣れ親しんでいるケースが少なくありません。DXへの抵抗感が根強い地域では、アナログ文化からの脱却が難しいこともあるでしょう。こうした自治体では、DX化の進捗状況で後れを取りやすい傾向にあります。
既存業務の負担
自治体の中には、現状の日常業務の負担が多く、職員が手一杯になってしまっている職場も存在します。DXで業務を削減する前に、そもそもDX推進に十分な時間を割けない場合もあるでしょう。まずはプロジェクトに必要なリソースを確保することが求められます。
自治体DXの進め方

前述したさまざまな課題がある中で、自治体はどのようにDXを進めれば良いのでしょうか。ここでは、実際に自治体DXを進めるステップをご紹介します。DX推進の大まかな流れを押さえておきましょう。
Step1.DXの認識を共有する
そもそもDX推進においてデジタル化自体は目的ではなく、あくまでも手段だといえます。組織内でDXの基本的な考え方をシェアし、認識共有から取り組み始めましょう。また、利用者中心の行政サービス改革を進める上では、サービスを使う人の立場を考慮しながら設計していく「サービスデザイン思考」を理解しておくことも大切です。
Step2.全体の方針を決定する
続いて、DX推進の施策を効果的に実施するために、全体的な方針を定めます。DX推進の意義やビジョンを自治体内で共有した上で、方針を検討すると良いでしょう。DX推進の具体的な取り組み内容について大まかな工程表を作成し、施策の順序や期間を明らかにします。
.png)
Step3.推進体制を整備する
組織内のDX推進の体制を整備します。体制の整備へ向けて、DX推進部門を設置するとともに、部門間で連携する仕組みを構築しましょう。また、人材の整備も必要です。DX推進リーダーを集中的に育成および確保し、同時に一般行政職員のデジタルリテラシー向上にも取り組みます。その際は、専門知識を有する外部人材を活用するのも一つの手です。
Step4.DXの取り組みを実行する
準備が完了したら、関連ガイドラインを踏まえて計画的にDX推進の施策を実行します。施策がスタートしたら進捗管理を徹底するとともに、実施後は振り返りと改善を繰り返してPDCAサイクルを回しましょう。施策の見直しが必要な場合は、適宜柔軟に変更へ取り組むのがポイントです。
【参考】「自治体DX全体手順書 【第2.1版】」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000857188.pdf
自治体DXにおける6つの重点取り組み事項

総務省の自治体DX推進計画では、以下の6つの取り組みが「重点取組事項」として定められています。現状、アナログな仕事が残されている地方自治体も少なくありません。デジタル社会の構築へ向けて、全自治体が着実に取り組みを進めることが重視されています。今後の業務改革で必要な取り組みを確認してみましょう。
自治体の情報システムの標準化や共通化
現状、地方自治体の業務で用いられている基幹系情報システムを、新たな標準仕様に準拠したシステムへ移行させる施策です。地方自治体における17つの業務を処理するシステムの標準仕様を、デジタル庁の基本方針のもとで関係府省が作成。クラウド活用を原則としたシステムへの移行によって、標準化や共通化を推進します。取り組みの目標時期は2025年度です。この施策の背景として、政府が提供するクラウドサービス「ガバメントクラウド(Gov-Cloud)」の構築と活用が挙げられます。
マイナンバーカードの普及促進
多くの自治体が引き続きマイナンバーカードの普及促進に取り組んでいます。例えば2025年3月時点では、マイナンバーカードの健康保険証利用、運転免許証利用などが進んでいる状況です。マイナンバーカードを活用することで、住民側は各種手続きの効率化や、ワンストップサービスによる利便性向上が期待できます。ただし、今後マイナンバーカードが普及するにつれて、自治体や警視庁・各都道府県の警察では、一時的な問い合わせ増加が懸念されています。
【参考】「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
【参考】「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」(警視庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html
行政手続きのオンライン化
地方自治体における各種行政手続きを、住民がマイナポータル上からマイナンバーカードを利用できるようにする施策です。具体的にマイナポータルから申請が想定される手続きとして、子育て関連、介護関連、被災者支援関連、自動車保有関連などが挙げられます。内閣府ではマイナポータルに地方自治体との接続機能を実装するとともに、UI・UX改善の面でも支援。また、マイナポータルと地方自治体の基幹システム接続をサポートしています。
AIやRPAの利用促進
地方自治体の基幹システム移行やオンライン化にともない、AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入および活用を進める施策です。AIやRPAの活用によって、これまで職員が行っていた作業を自動化し、効率化できる可能性があります。そのためにも、総務省ではAI・RPAの導入ガイドブックの策定や、業務プロセスの標準モデル構築などに取り組み、利用推進を支援している状況です。また、総務省および内閣官房では、利用推進へ向けたデジタル人材の確保・育成といった支援が行われています。
群馬県前橋市の国民健康保険課では、住民からの電話を自動音声応答システムで振り分け、業務効率化を実現しました。電話業務を自動化した自治体の事例は、以下のページからご覧ください。
【参考】ひっきりなしの電話を自動音声応答システムで振り分け、時間の余裕をつくる。
テレワークの推進
民間企業で普及が進みつつあるテレワークを地方自治体でも導入し、利活用を進める施策です。地方自治体でテレワークを実現するにあたり、総務省ではセキュリティポリシーガイドラインを改定し、スムーズな導入を支援しています。また、セキュリティ性の高い自治体独自ネットワーク「LGWAN-ASP」による安全なテレワーク環境の確保のほか、地方自治体のテレワーク導入事例の提供といったサポートが行われています。今後は基幹システム移行やオンライン化の状況次第で、テレワークの導入対象となる業務が拡大されていく見込みです。
セキュリティ対策の徹底
業務でのセキュリティ対策を徹底するために、改定セキュリティポリシーガイドラインに従って、現状のセキュリティポリシーの見直しを行う施策です。地方自治体におけるデジタル活用では、個人情報を扱うことからセキュリティ性の高さが求められます。巧妙化するサイバー攻撃の手口に備えて、迅速に対策を講じるとともに、公務員のITリテラシーを高める必要があります。総務省では2020年にセキュリティポリシーガイドラインの改定を実施しました。また、情報システムの標準化・共通化を踏まえて、新たなセキュリティ対策を検討するなど、安全性の確保を支援しています。さらに、2020年にはセキュリティ強化のため次期自治体情報セキュリティクラウドへの移行をサポートしています。
【参考】「自治体DX推進計画概要」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000727132.pdf
自治体のDX推進への取り組みの事例

最後に、総務省が公表する「自治体DX推進参考事例集」の中から、DX推進に成功した自治体情報をご紹介します。全国の市区町村では、DX推進によって具体的にどのような改善を実現できたのでしょうか。ぜひ先進事例や推進状況を今後の施策の参考にしてみてください。
【出典】総務省「自治体DXの推進」
https://www.soumu.go.jp/denshijiti/index_00001.html
マイナンバーカードを利用した電子申請・届出システム【岡山県鏡野町】
岡山県鏡野町では、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した「鏡野町申請・届出システム」を導入しました。これにより、住民は各種申請・届出・補助金などの交付申請をオンラインで行えるようになります。さらに、証明書などを郵送請求する際は、クレジット決済で手数料を支払うことが可能です。加えて、役場窓口ではタブレットとマイナンバーカードを活用して申請書を印刷する仕組みが採用されています。これにより、役場窓⼝への来訪不要、キャッシュレス決済導入、手続きのスマホ完結、電子化にともなう申請書類の手書き不要といった多くのメリットを実現できました。
【参考】https://www.soumu.go.jp/main_content/000879053.pdf
オンライン相談ツールの活用による「行かなくて済む区役所」の取組【東京都】
東京都では、住民の相談へオンラインで対応するために、新たにビデオ通話システムを導入しました。オンライン相談が始まった背景として、新型コロナウイルス感染拡大にともない対面による相談業務の休止を余儀なくされた事情があります。しかし、現在はこれまで相談窓口へ来られなかった方の支援まで視野に入れ、気軽に利用しやすいオンライン相談の対応範囲を拡大している状況です。現在提供されている相談の範囲は、法律相談・司法書士相談・行政書士相談・住まいの増改築相談・ひきこもり専用相談といった分野まで広がっています。
【参考】https://www.soumu.go.jp/main_content/000879053.pdf
県と県内市町による高度デジタル人材シェアリング事業【愛媛県】
愛媛県では、「チーム愛媛DX推進支援センター」を設置し、県が確保した高度デジタル人材を県内の市町とシェアする仕組みを構築しました。DX推進に不可欠なデジタル人材は、自治体に限らず民間企業でも全国的に不足しており、人材確保が難しい傾向にあります。そこで愛媛県は、県で確保したデジタル人材を市町とシェアすることで、人的・財政的負担を軽減する施策を実施しました。DX推進支援センターがコミュニケーションの動線となり連絡調整を効率化し、県内広域で質の高いDX推進を実現しています。
【参考】https://www.soumu.go.jp/main_content/000878977.pdf
デジタル技術を主体的に活用できるDX推進チャレンジャーを育成【滋賀県】
滋賀県では、役所のさまざまな業務の担当職員が自律的にDX推進へ取り組める体制づくりを目的として、「DX推進チャレンジャー(=デジタル技術を主体的に活用できる職員)」を育成しています。人材育成によって、各分野の業務に精通した職員がデジタル技術を活用するスキルを身に着け、幅広い部署でDXを推進することが可能です。令和4年度から6年度までの3年間で育成されたDX推進チャレンジャーの人数は450人に達し、一般行政部門などの職員の10~15%に相当する人材を育成できました。
【参考】https://www.soumu.go.jp/main_content/000878977.pdf
全59市町村へのICTアドバイザー派遣等にて市町村のDXを底上げ【福島県】
福島県では、「ICTアドバイザー(=ICTの専門家)」を市町村へ派遣する事業によって、DX推進を支援しています。県内では7~8割の市町村がDXにおいて人材・知見の面での不足を実感しているのが課題です。そこで、市町村へ専門家を派遣する支援策で、DXの課題解決を重点的にサポート。連携強化によって県全体のDX推進体制を支援し、効率的な行政運営や住民サービスの向上を目指します。また、専門家の派遣のほかに「市町村DX推進トップセミナー事業」を実施し、研修を通じた市町村のDX推進へ向けた意識の底上げにも取り組んでいます。
【参考】https://www.soumu.go.jp/denshijiti/digital_transformation_portal/case/dx1_04.html
知事のもとデザイン思考に基づくDXを全庁横断的に推進中【大分県】
大分県では、知事がCXO(チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー)となる「大分県DX推進本部」を設置し、全庁体制で県民中心のDX推進に取り組んでいます。大分県DX推進本部会議が、DX推進戦略を策定し、全庁の指揮やフォローアップを実施。各部署では、DX推進課や外部アドバイザーからの支援を受けながら、デザイン思考による施策立案や実施を担います。この取り組みにあたり、大分県では全ての県職員に対して研修を実施しているのもポイントです。県民をユーザーとして、顧客体験を重視したDX推進に取り組んでいます。
【参考】https://www.soumu.go.jp/denshijiti/digital_transformation_portal/case/dx1_13.html
自治体DXの取組とあわせて取り組むべき事項

自治体DXを推進するにあたり、あわせて「地域社会のデジタル化推進」や「デジタルデバイド(格差)の解消」にも取り組むのが望ましいでしょう。
例えば、地域社会のデジタル化推進へ向けて、高速通信網や情報通信基盤を整備する必要があります。そこでは地域特性に合ったデジタル技術を導入することもポイントです。また、近年は社会の高齢化とデジタル化の進行にともない、デジタルデバイド(=ITの恩恵を受けられない人に生じる情報格差)の解消が急務となりました。自治体では、高齢者・デジタル初心者向けの支援を強化する必要があります。具体的には、相談窓口の設置やサポート体制の充実化を図ると良いでしょう。
【参考】 「地域社会のデジタル化に係る参考事例集[第3.0版]」(総務省)
URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000949882.pdf
自治体DXで業務効率化と利便性向上を目指しましょう!
ここまで、自治体DXについて解説しました。デジタル技術がより便利な社会を実現している今、地方自治体でもデジタル技術の導入やデータ活用で新たな価値を創出していく必要があります。自治体DXでこれまでの業務を見直し、業務改革へ取り組みましょう。電話放送局では、電話業務の分野でDX推進に貢献するソリューションをご用意しています。例えば「電話取り次ぎDX とりつぎ君」では、AIとボイスボットを組み合わせたシステムで、代表電話の取り次ぎを完全自動化することが可能です。職員数の少ない部署での電話業務の負担を軽減し、業務効率化やサービス品質向上に役立ちます。自治体DXの一環で電話業務を見直す際は、どうぞお気軽に電話放送局へお問い合わせください。
とりつぎ君
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、自治体の電話業務をIVR(ボイスボット)で、自動化する活用事例、業務改善のポイントを知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・自治体のどのような電話業務に活用できるのか知りたい
・自動化に適した各部署の業務内容を知りたい
・IVR(ボイスボット)やオートコールの具体的な活用事例を知りたい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(3)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711