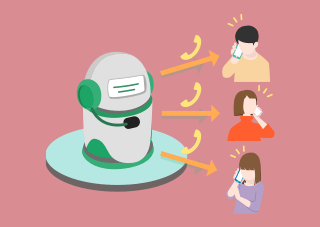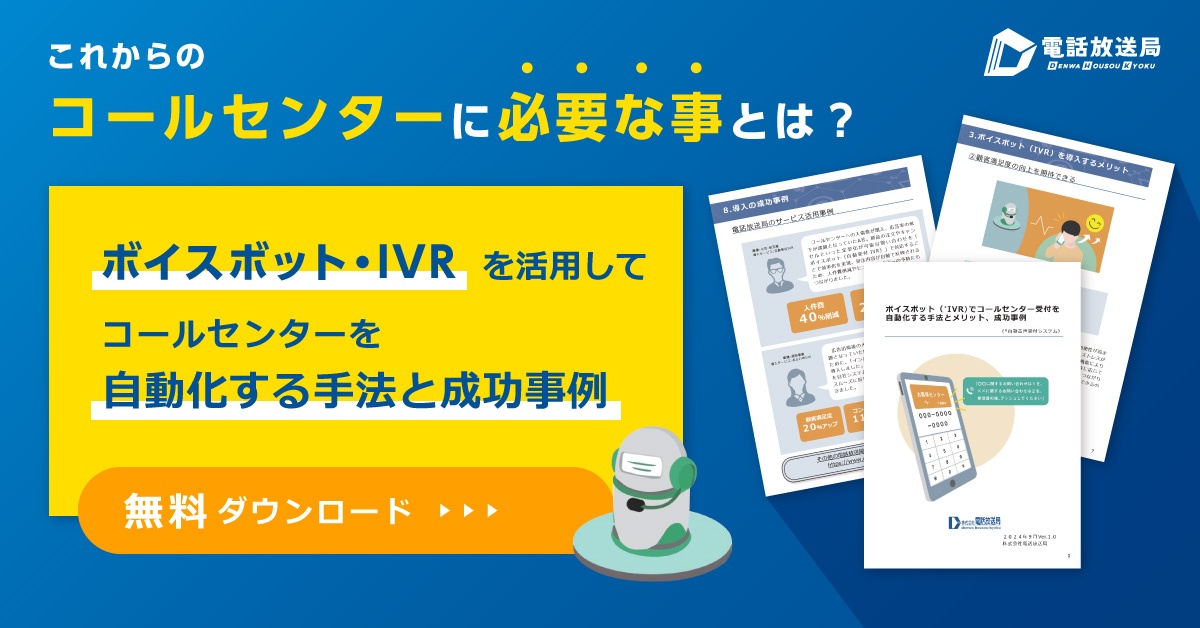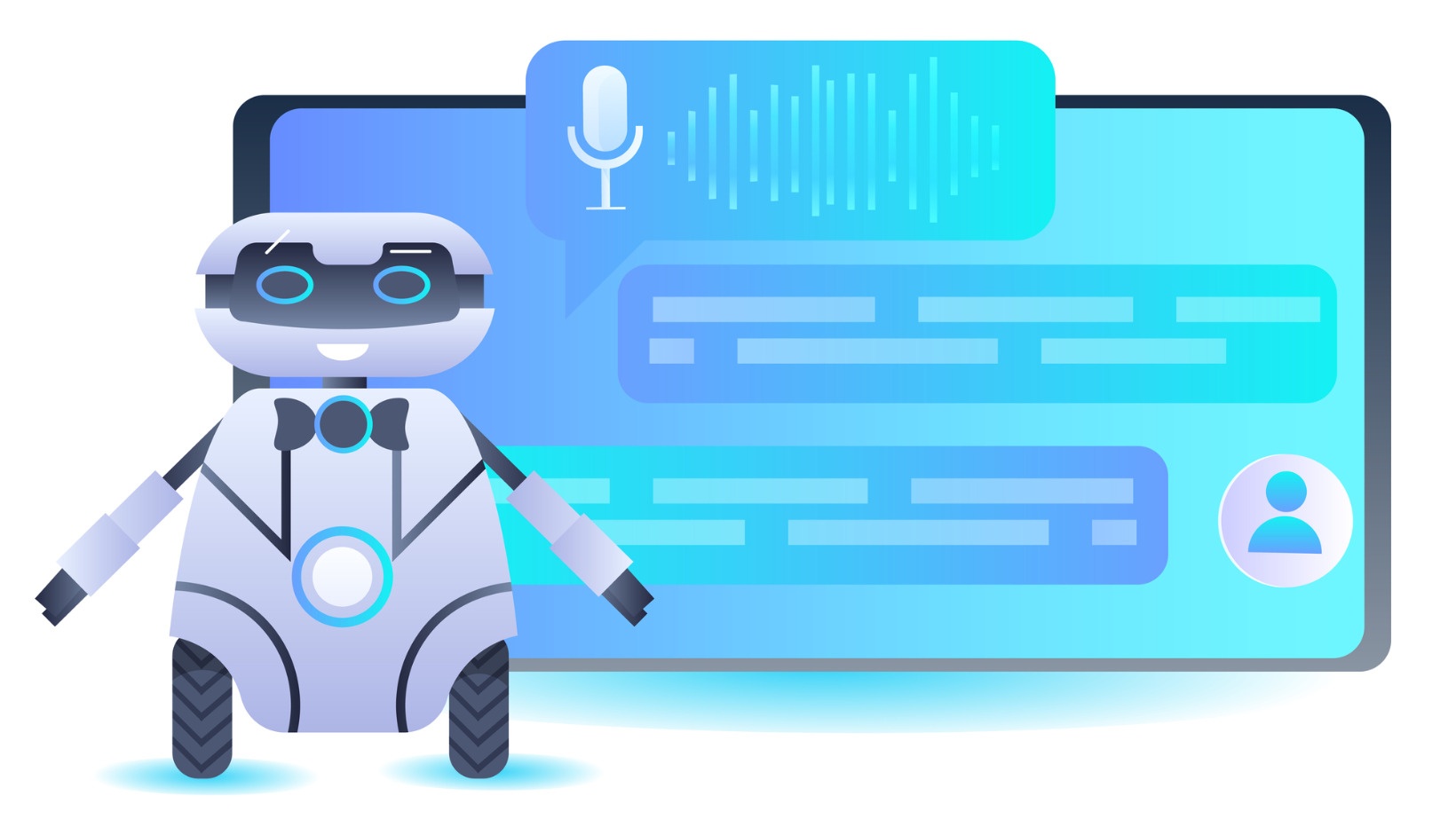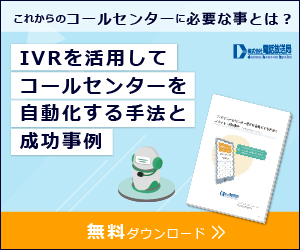コールセンターは高齢者対応の強化が必要?課題や対応時のポイント
2025/04/22

社会の高齢化による影響は、コールセンター(コンタクトセンター)業界にまで広がっています。高齢の顧客が多い場合、オペレーターは高齢者に配慮した接客を意識する必要があるでしょう。コールセンターの高齢者対応では、具体的にどのようなポイントを意識すれば良いのでしょうか。
本記事では、コールセンターの高齢者対応の強化について解説します。シニア世代の電話対応でよくある課題や、高齢者対応のポイントまでお伝えするため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
・コールセンターの高齢者対応の改善にはIVRやボイスボットが効果的!
コールセンターで高齢者対応の強化が求められる背景

近年はなぜコールセンターでシニア世代への対応強化が重視されているのでしょうか。初めに、社会の高齢化をはじめとした背景をご紹介します。
社会全体の高齢化
内閣府が公表する資料「令和6年版高齢社会白書」によると、2023年10月1日時点における65歳以上人口は3,623万人で、日本の総人口に占める割合は29.1%となっています。高齢化率は年々高まる傾向にあり、2070年には38.7%に達すると推計されています。さらに、2070年には国民の約2.6人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上になると予測されている状況です。すでに高齢化社会を迎えた日本では、今後カスタマーサポートにおいても高齢者への対応力がますます重要になると考えられています。
【出典】「令和6年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第1章 高齢化の状況 第1節 高齢化の状況」(内閣府)
コールセンターを利用する高齢者の増加
株式会社リックテレコムが発行する「月刊コールセンタージャパン」編集部の調査によると、コールセンターへ問い合わせをする顧客層が年々高齢化している現状が明らかになっています。同社による2022年の調査では60代以上からの問い合わせが38.4%であったのに対して、2023年の調査では43.3%まで上昇する結果となりました。なかでも2023年における通信販売の分野に注目すると、60代以上の顧客が問い合わせの56.3%を占めている状況です。コールセンターのサービスにおいて、シニア層の利用がさらに顕著になっています。
【出典】 「2023年8月号 <第2特集>コールセンター利用者調査2023」 (月刊コールセンタージャパン)
コールセンターにおける高齢者対応のポイントと課題

コールセンターでシニア世代の顧客対応を行うにあたり、どのような課題があるのでしょうか。ここでは、主な課題や具体的な電話対応のポイントを解説します。高齢者対応を視野に入れて、業務マニュアルや研修プログラムの見直しをご検討ください。
コールセンターにおける高齢者対応の主な課題
・聞き取りづらさへの対応
一般的に、加齢による身体的な変化で聴力が低下する人が多いことから、コールセンター業務ではシニア世代の聞き取りづらさへの配慮が求められます。オペレーターが通常の声量やスピードで対話すると、顧客が声を聞き取れないおそれがあります。
・理解力・記憶力への配慮
コールセンターの接客では、シニア世代の情報処理速度や記憶力の低下にも配慮が必要です。一度の説明で顧客に内容を理解してもらえない場合、オペレーターは相手が理解できるまで繰り返し説明を求められる可能性があるでしょう。
・感情面の配慮と対応時間の確保
電話口での印象が「冷たい対応」「機械的な言い回し」として受け取られると、シニア世代の顧客に不信感を与えるおそれがあります。通常よりもやりとりに多くの時間がかかることを踏まえて、コールセンター運営では長めの応対時間を想定した人員配置が必要となります。
コールセンターにおける高齢者への対応ポイント
・話し方を工夫する
高齢の顧客との会話では、「ゆっくり」「はっきり」「丁寧に」を意識して話すことが基本です。また、シニア世代が聞き慣れない専門用語や略語の使用はできるだけ避けて、誰でも理解しやすい身近な表現に置き換えて伝えると良いでしょう。
・内容を繰り返す・確認する
高齢の顧客は内容を一度で理解するのが難しい場合があるため、話の要点は繰り返し説明することが大切です。その際は、オペレーター側がこまめに「この内容でよろしいでしょうか?」と確認を挟むことで、互いに認識のズレを防ぎやすくなります。
・共感を示す
高齢の顧客に安心感を与えるには、傾聴スキルが役立ちます。特にクレーム対応では、「ご不便をおかけして申し訳ありません」「お気持ち、よくわかります」といった共感の言葉を意識的に使いましょう。相手に寄り添う言葉がけによって、顧客の不安を和らげやすくなります。
コールセンターの高齢者対応をスムーズにするには

コールセンターにおいて高齢者の電話応対がますます重要となっている一方で、現場ではオペレーターの負担増加が懸念されています。業務改善の施策として、IVR(自動音声応答システム)やボイスボットの活用をご検討ください。ここでは、コールセンターの高齢者対応をスムーズにするポイントを解説します。
高齢者対策にIVRやボイスボットを導入するメリット
コールセンターにIVRやボイスボットを導入すると、オペレーターに電話がつながる前に顧客の目的に適した振り分けが可能となるため、待ち時間を短縮できるのがメリットです。また、定型的な問い合わせを自動応答で解決できるようになるため、オペレーターは複雑な問い合わせに集中しやすくなり、業務負担の軽減が期待できます。
IVRやボイスボット導入時のポイント
・メニューをシンプルにする
シニア世代が電話口の操作で迷ってしまうのを防ぐために、IVRやボイスボットにはシンプルなメニュー設計を採用し、必要に応じて速やかにオペレーターにつなぐ選択肢を提示しましょう。また、音声ガイダンスの音量やスピードは高齢の顧客に配慮して、聞き取りやすいように調整することが重要です。
・SMSでのサイト誘導とビデオ通話の活用
問い合わせの目的によっては、SMS(ショートメッセージサービス)でFAQサイトへ誘導する方法や、ビデオ通話を活用する方法も検討しましょう。スマートフォンで画像や動画を見ながら説明したほうが、視認性が改善されて内容が伝わりやすいケースがあります。特にSMSによる案内は、顧客が必要な情報へ簡単にアクセスでき、わかりやすい画像や動画で問題の自己解決を促せるのがメリットです。
【参考】※パートナーサイト
オンラインでの住民相談をビデオトークでかんたんに実現
IVRについてさらに詳しく知りたいご担当者様は、以下の関連記事をご覧ください。導入メリットやサービスの選び方まで解説しています。
【関連記事】
・IVRとは?特徴やコールセンターに導入するメリット、サービスの選び方
・ボイスボットとは?メリット・デメリットや活用方法、選定ポイント
コールセンターの高齢者対応の改善にはIVRやボイスボットが効果的!
ここまで、コールセンターの高齢者対応の強化へ向けて、シニア世代の電話対応でよくある課題や、高齢者対応のポイントを解説しました。国内は高齢化社会を迎え、多くのコールセンターで顧客層の高齢化が進んでいます。高齢者対応のために職場の業務フローを見直す必要性を感じている管理者の方も多いのではないでしょうか。その際は、顧客満足度を高めるIVRやボイスボットの活用をご検討ください。
ノーコード ボイスボットの「DHK CANVAS」は、自社の電話業務に合わせて柔軟にIVRのコールフローを設定できるのが魅力です。また、「オートコールIVR」ではコールフローに応じて顧客へSMSを自動送信できます。顧客の問い合わせの目的に応じて、わかりやすい方法で問題解決を支援することが可能です。コールセンターの業務効率化でお悩みの際は、お気軽に電話放送局までご相談ください。
DHK CANVAS
オートコールIVR
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、ボイスボット・IVRを活用した電話業務を自動化する手法や、ボイスボット・IVR提供会社を選ぶポイントを知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・コールセンターの電話業務をどこまで自動化できるのか知りたい
・自動化に適したコール内容を知りたい
・ボイスボット、IVR導入により、自動化に成功した事例を知りたい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(3)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711