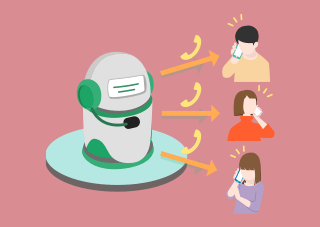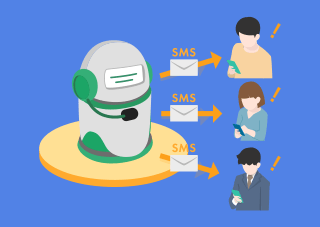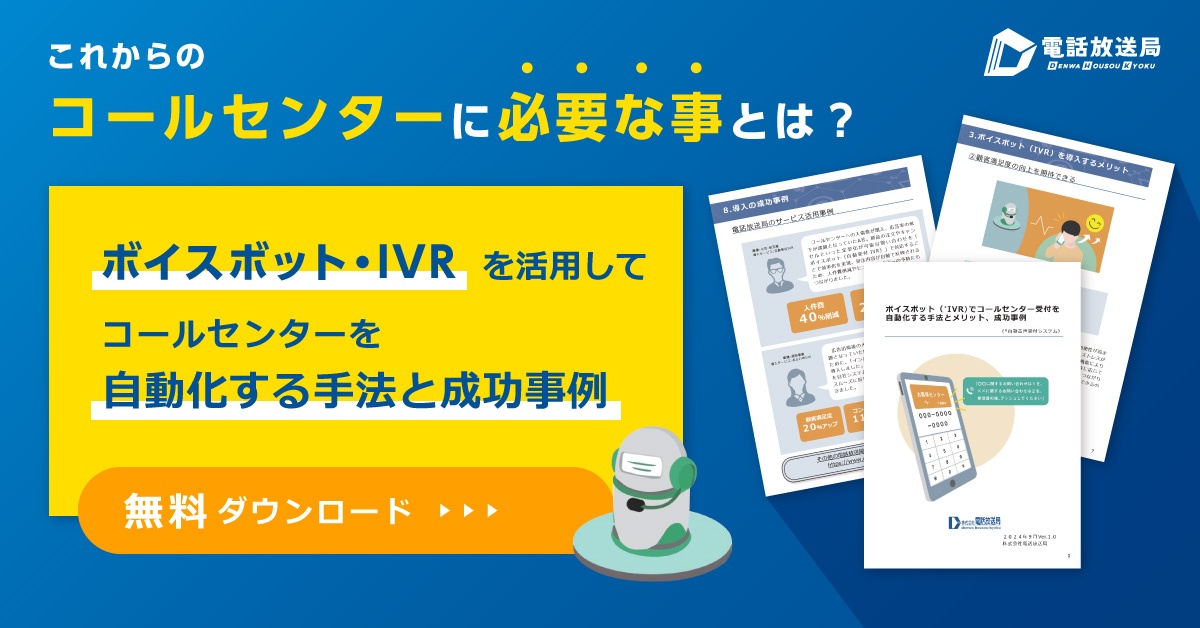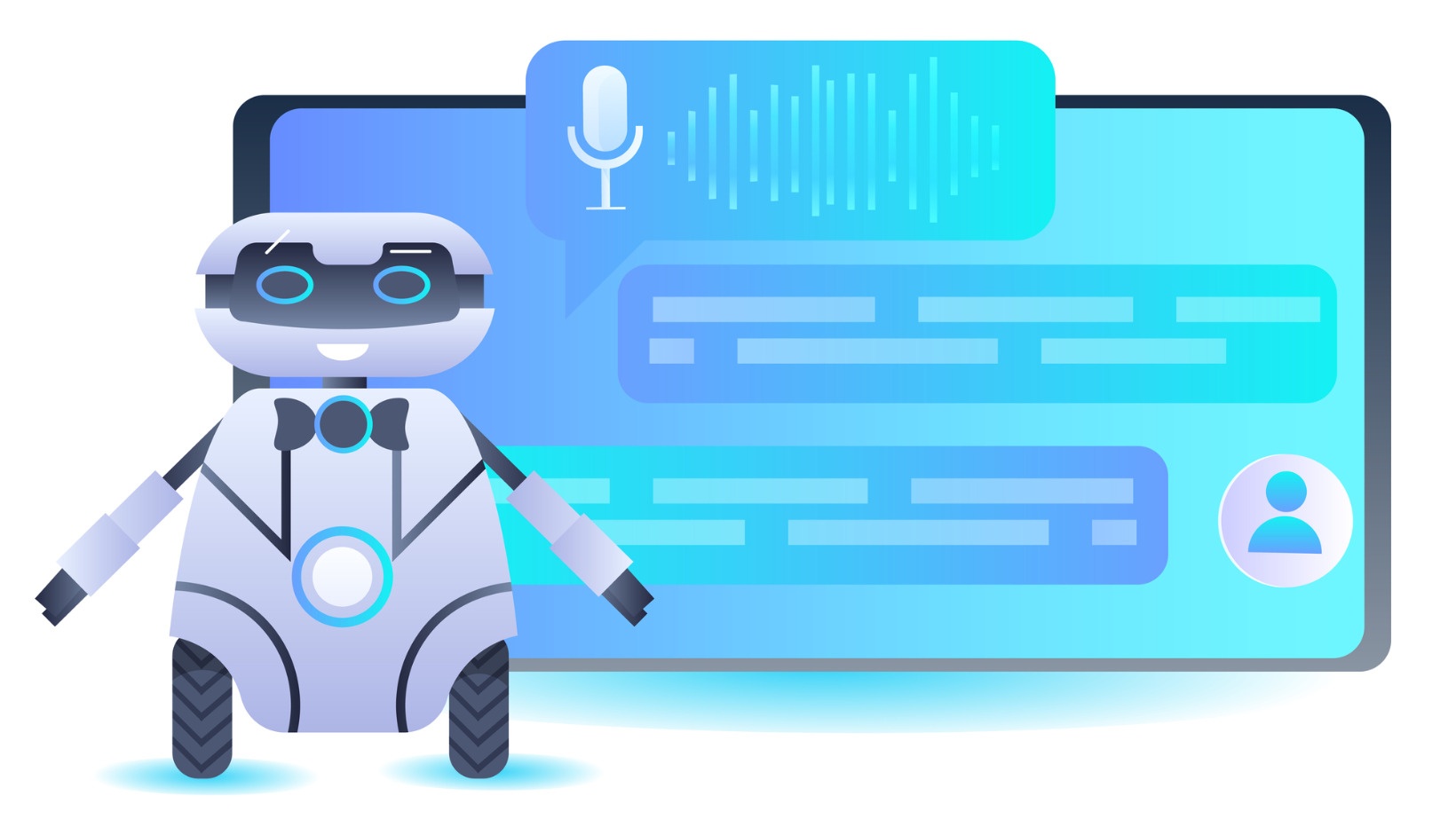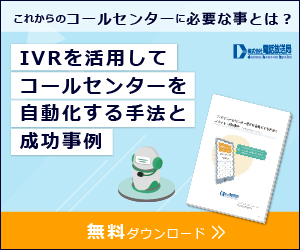FAXDMのメリット・デメリットは?読まれるために押さえたいポイント
2024/12/26

FAXDMとは、FAXの送信先に自社の商品・サービスの情報を直接届ける営業手法です。法人リストにFAXを一斉送信することで、効率的かつ効果的にターゲットへアプローチします。郵送のDMと比べて1枚あたりにかかる費用や手間を抑えられるので、集客の費用対効果の高さが特徴です。近年、インターネット上で配信するDMが主流となる中、BtoBのマーケティングにFAXDMを利用する企業も少なくありません。
この記事では、FAXDMのメリット・デメリットや、送信したFAXDMを顧客に読んでもらうためのノウハウを解説します。また、FAXDMと併せて検討したいおすすめのマーケティングの手法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
・FAXDMによるマーケティングを見直すならIVRやSMSの手法がおすすめ
FAXDMのメリット・デメリット

初めに、FAXDMのメリット・デメリットを解説します。紙媒体で送るチラシとの違いや、電子データで送るメールとの違いなど、他のマーケティング手法と比べながら改めて特徴を確認してみましょう。
FAXDMのメリット
・大量送信が可能
FAXDMは宛先リストへ一斉送信する仕組みなので、一度に広範囲の宛先へ情報発信が可能です。大量の件数にも簡単に対応できます。また、相手の電話番号(FAX番号)さえ分かれば送信可能な点もメリットだといえます。リスト作成の際、顧客の住所やメールアドレスを収集する必要がありません。
・即時性が高い
FAXDMは、チラシなどの紙媒体と同様に物理的に手に取ってもらえる性質を持ちながら、タイムリーに情報を届けられます。郵送で送付するよりも速やかに配信できるので、即時性の高さもメリットです。期間限定のキャンペーンやセール情報のようなプロモーションでも効果を発揮します。
・コストパフォーマンスが良い
FAXDMは、他の手法と比べて1件あたりの単価を抑え、低コストで配信できます。例えば、ハガキや封筒を使うDMでは、デザイン代・紙代・印刷代・郵送代などが発生します。それに対してFAXDMは、社内で宛先リストを作成し、原稿制作と配信手続きを行うだけで完了するので、コスト削減が可能です。
FAXDMのデメリット
・カラービジュアルが使えない
FAXDMは仕様の都合上、基本的にカラービジュアルが使えないので、書面が白黒になります。なかにはカラー対応の機種もあるものの、受信側がカラー対応の機種を導入しているとは限りません。紙媒体のようにカラービジュアルを生かして視覚的にアピールするのは難しいでしょう。
・広告を見てもらえる割合があまり高くない
FAXDMの反響率(=広告を見て反応してくれる人の割合)の目安は0.1~0.3%程度とされています。そのため、受信側から反響を得るには一定以上の件数に配信する必要があるでしょう。また、近年の複合機や電話機にはモニターでプレビューする機能が搭載されているので、担当者にFAXDMが不要と判断されると印刷されずに削除されてしまう可能性があります。
FAXDMに記載する内容

FAXDMを作成する際は、一般的に以下の内容を記載します。自社の商材の魅力を適切に案内し、新規開拓を成功へ導くために、これらの内容をもれなく盛り込みましょう。
見出し
FAXDMの見出しでは、顧客にとって重要な情報が一目で分かるようにするのがコツです。キャッチーで簡潔な見出しをつけましょう。商材に関する重要なキーワードを盛り込んで、手に取った瞬間に興味を持ってもらうことが大切です。
本文
FAXDMでお知らせしたいメインの内容を、文章や図表などで表現します。その際は、A4のコピー用紙サイズに情報を収める必要があります。印刷は顧客の負担になるので、枚数は基本的には1枚に留めるのが望ましいでしょう。本文を書くときは、顧客が即座に内容を理解できるよう、ポイントを絞って情報を盛り込みます。全ての内容を読んでもらえるとは限らないため、伝えたいメッセージを簡潔にまとめましょう。
配信元の情報
FAXDMには配信元の企業名や担当者名を明記しましょう。配信元がわかることで信頼性が高まり、顧客の安心につながります。また、顧客が問い合わせや資料請求の申し込みをする際に必要な、企業の住所や連絡先などの情報も忘れずに記載してください。
レスポンスデバイス
レスポンスデバイスとは、FAXDMを受け取った人が問い合わせるための連絡手段のことです。具体的には、FAXDMにQRコードを掲載し、専用の問い合わせフォームへ誘導する方法などが挙げられます。顧客の次のアクションを促す対策を取り入れましょう。
FAXDMが読まれるために押さえたいポイント

FAXDMは顧客に読まれる前に破棄されてしまう可能性があります。顧客の興味を引き、手に取って読んでもらうためにも、以下のポイントを意識してFAXDMを作成しましょう。
受け取る相手が理解しやすい内容にする
FAXDMの原稿制作では、顧客に必要な情報を的確に届ける工夫をしましょう。簡潔でわかりやすい言葉遣いを心がけ、業界用語や専門用語の多用は避けます。また、文章量が多くなるほど文字が小さくなり、読みづらくなる点にも注意が必要です。内容は最小限に留め、より詳細な情報は問い合わせ後にサービス資料などで伝えると良いでしょう。
目を引く見出しや見た目を重視する
FAXDMではカラービジュアルが使えないので、デザインでメリハリをつけるよう意識し、顧客を視覚的に引きつけることが重要です。特に見出しの部分は、重要な情報を目立たせなければなりません。キャッチーで読みやすいフォントを選んだり、文字サイズを大きくしたりと、手に取った人が内容を読みたくなるような工夫を凝らしましょう。
送信するタイミングや頻度も考慮する
FAXDMは送信するタイミングや頻度によって、読まれるかどうかに差が出ます。事前に顧客の業務時間や多忙な時期をリサーチして、タイミングに配慮して配信しましょう。また、定期的に配信すると顧客に覚えてもらいやすくなります。印象に残りやすくなるよう、配信の頻度を調整すると良いでしょう。
FAXやFAXDMは今後どうなっていく?

ここまでお伝えしたように、FAXDMにはさまざまなメリットがあるものの、現在はFAXを保有する世帯が減少傾向にあるのが注意点です。総務省が公表する「令和5年 通信利用動向調査報告書(世帯編)」の資料によると、FAXの保有率は年々減少傾向にあり、2023年には26.9%にまで落ち込んでいます。2013年の46.4%と比較して、10年間で20%近く減少しました。FAX自体が完全になくなることは考えにくいものの、今後も保有率は下がると見込まれています。
こうした状況から、ビジネスシーンで電話を用いたコミュニケーション手段として、自動で架電する「オートコール」や、自動でテキストメッセージを配信する「SMS(ショートメッセージサービス)」などが主に利用されています。FAXの保有率の推移にともない、FAXDMからの移行を検討する企業も多くなっています。あるいは、FAXDMをオートコールやSMSと掛け合わせて、双方の強みを生かして運用するのも一つの手です。
【出典】「令和5年 通信利用動向調査報告書(世帯編)」(総務省 情報流通行政局)
FAXDMによるマーケティングを見直すならIVRやSMSの手法がおすすめ
ここまで、FAXDMのメリット・デメリットや、顧客にFAXDMを読んでもらうためのノウハウを解説しました。FAXDMは数あるマーケティング手法の中でも比較的安価で行える施策ですが、近年は情報の伝達手段が多様化し、FAXを利用する企業は減少傾向にあります。そのため、FAXDM以外にも新規開拓の手段を検討すると良いでしょう。
FAXDMと同様に、費用や手間を抑えながら多数の企業へ効率的にアプローチするなら、オートコールやSMSなどの手法がおすすめです。電話放送局では、営業活動に役立つ便利な電話サービスをご用意しています。
「オートコールIVR」は、大量回線で一斉に顧客へアプローチできる自動架電サービスです。顧客へ声によるDMを届ける新たな販促ツールとして、手軽にマーケティングに活用できます。発信する時間帯を設定できるので、顧客が電話に出やすいタイミングで効果的なアプローチを実現します。
「SMS送信Web」は、顧客の携帯電話番号宛に自動でテキストメッセージを送信できるサービスです。携帯電話・スマートフォンに初期状態でインストールされているアプリを利用するので、番号のみで着実にメッセージを届けられます。低コストかつタイムリーに一斉配信できるのが魅力です。
FAXDMによるマーケティングを見直すなら、IVRやSMSをはじめとした多彩なサービスを提供し、サポートが手厚い電話放送局へお問い合わせください。
オートコールIVR
SMS送信Web
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、ボイスボット・IVRを活用した電話業務を自動化する手法や、ボイスボット・IVR提供会社を選ぶポイントを知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・コールセンターの電話業務をどこまで自動化できるのか知りたい
・自動化に適したコール内容を知りたい
・ボイスボット、IVR導入により、自動化に成功した事例を知りたい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(4)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAQ(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711