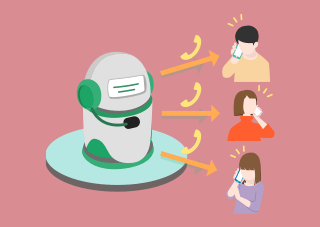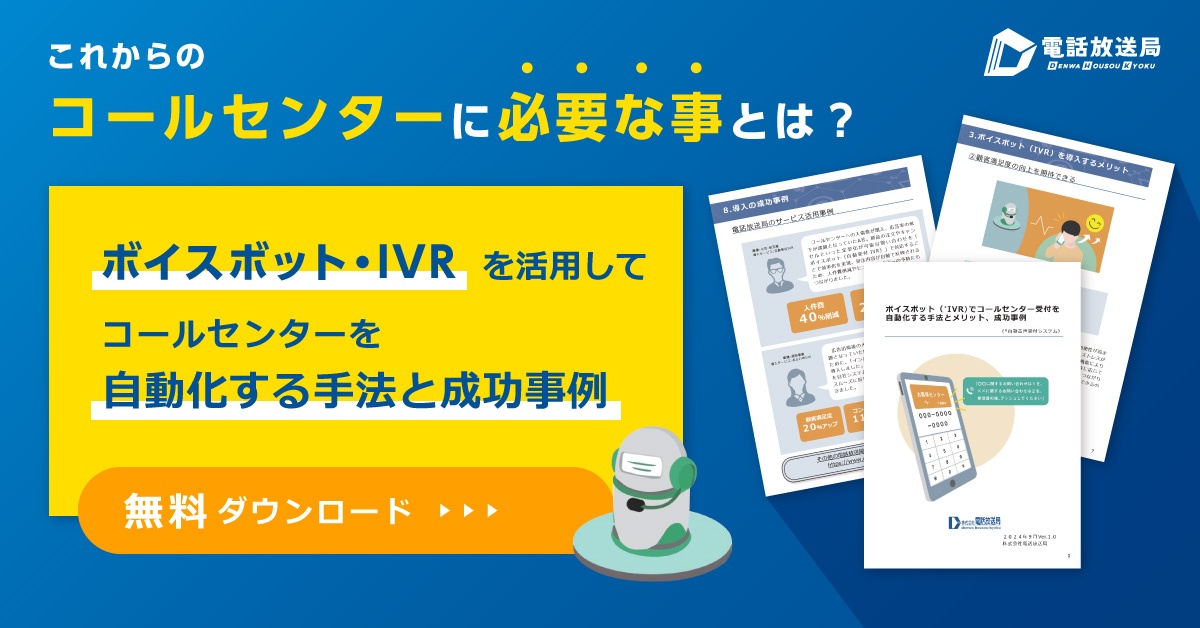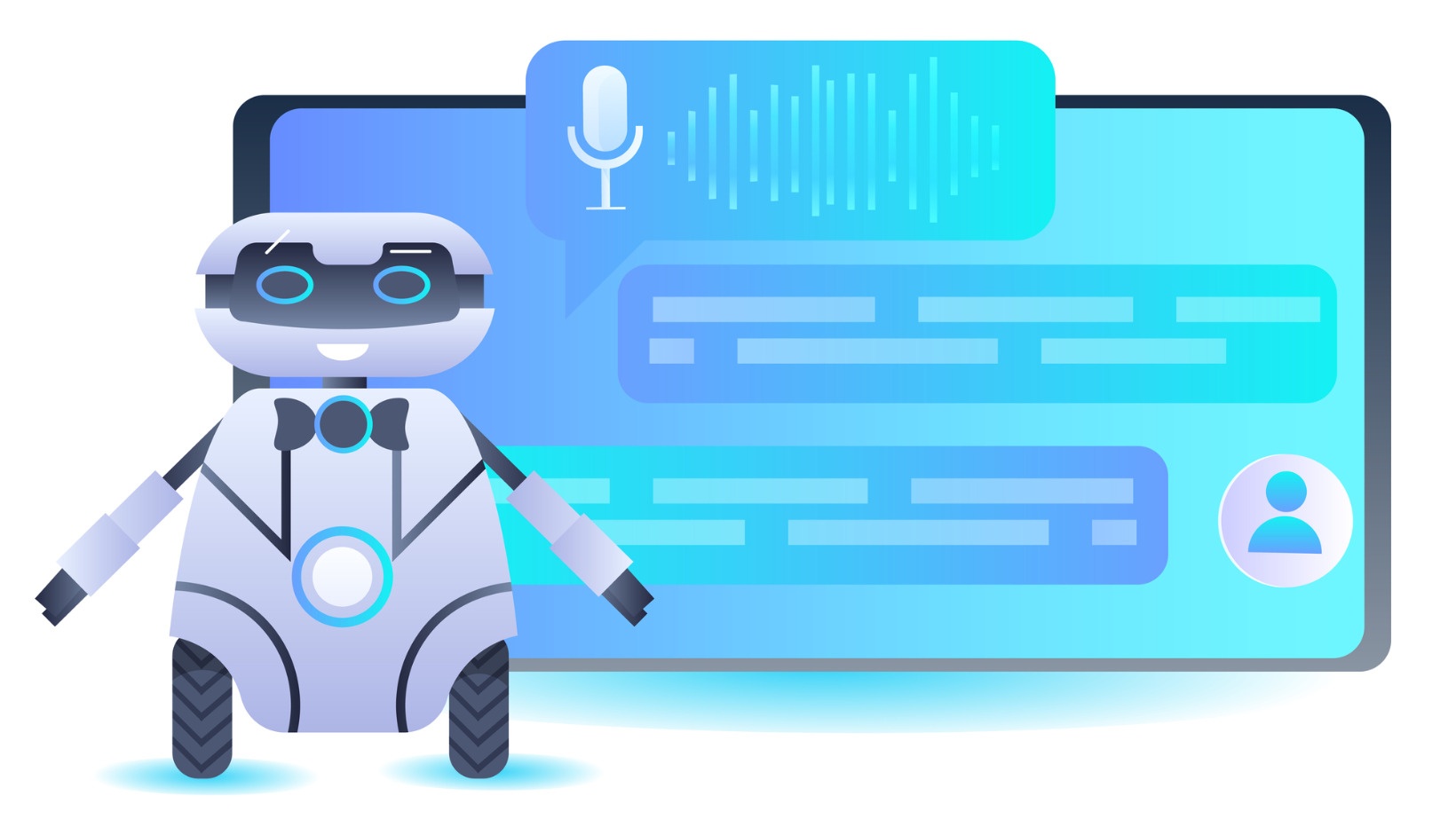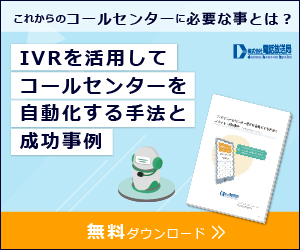金融DXとは?メリットや課題|取り組み事例と推進する際のポイント
2024/09/05

近年は注目の「FinTech(フィンテック)」への参入やキャッシュレス化をはじめとして、金融業界でもデジタル戦略に注力する動きが加速するようになりました。最先端のデジタル技術を活用することで、既存の業務プロセスを改善したり、新規サービスを創出したりできる可能性があります。ビジネスでの優位性を確保するために、金融機関・保険会社・証券会社・などの金融企業でも積極的にDX推進へ取り組み始めましょう。
DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語です。デジタル技術を活用したビジネスの変革のことを指し、取り組みにより企業の成長や競争力強化などを実現します。国内では経済産業省がDX推進を主導し、金融業界でも多くの企業が取り組んでいる状況です。
本記事では、金融業界のDXについて解説します。DXを導入するメリットや業界の課題、導入事例までご紹介するため、ぜひ参考にお読みください。
目次
金融DXとは?

金融DXとは、金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)のさまざまな取り組みを指します。具体的には、現状の金融サービスや業務プロセスのデジタル化を促し、新規サービスの創出や業務改革につなげることなどが該当します。 そこでは、施策の一環として「FinTech(フィンテック)」などの新たな分野に参入するケースや、IoTやRPAといったデジタルツールを活用するケース 、既存システムの変更や改修に取り組むケースも少なくありません。ただし、DXは単なるデジタル化とは区別されており、最終的にビジネスの成長や競争力強化を実現することが重要視されています。
金融DXのメリット

金融業界の企業がDXを導入すると、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。企業側のメリットだけでなく、ユーザー側にもたらされるメリットにも注目です。ここでは、金融DXで実現できることをご紹介します。
AIの導入による業務の効率化
定型的な業務にAIを導入すると、一部の業務が自動化され、業務効率の向上やコスト削減が期待できます。たとえば金融機関の電話窓口では、よくある質問への回答や手続きなどの定型的な作業が行われています。そこでチャットボットを導入すると、一部の対面での顧客対応を自動化して時間を短縮し、定型業務の負担を軽減できるのです。加えて、担当者のリソースを有効活用して、重要度の高い問い合わせへ優先的に対応しやすくなります。テクノロジーの活用によって顧客対応の人員を削減しながら、サポートの充実化をはかり利便性を高められます。人材不足の対策としても効果的です。
セキュリティ技術の導入による安全性の向上
金融業務における本人確認に生体認証技術を導入すれば、セキュリティの強化が期待できます。たとえば、銀行のATMやインターネットバンキングのアプリにおける取引では、指紋認証による本人確認が行われています。これにより、預金者本人を偽って預金を引き出すなど、第三者によるなりすましの防止が可能です。金融業界のビジネスモデルでは、取り扱う商品の性質などの理由から、顧客サービスでは特に強固なセキュリティが求められます。最新のセキュリティ技術で安全性が向上し、迅速な認証による顧客体験の改善も期待できます。
クラウドの導入による金融サービスの高度化
金融業務では膨大な量の情報を取り扱います。これらのビッグデータをクラウドで管理することで、データ活用を推進したり、スムーズなデータ共有で社内の連携を強化したりできます。たとえば、金融機関の取引データをクラウドに蓄積して、顧客情報をデータ分析に活用する方法です。これにより融資業務の効率化や、判断の正確性アップが期待でき、営業活動やサービスの高度化に寄与します。また、クラウドの運用体制を整備すると、オンラインサービスで新たな顧客接点を創出するほか、データ量の増加や最新技術の導入に対応しやすくなる点でもメリットが大きいといえるでしょう。
金融DXにおける課題
.jpg)
現状の金融業界では、レガシーシステムへの依存が問題視されています。レガシーシステムとは、古い技術で構築されているために、改修や保守運用の負担が大きいシステムのことです。金融業界ではかつて、ほかの業界よりも早期に業務システムが導入されました。しかし、その後に各社がシステムに独自の改修を重ねた結果、システムが巨大化・複雑化したケースが少なからず見受けられます。
こうしたレガシーシステムは、最新の技術では改修や保守運用に対応できないことから、維持コストがかさみやすいのが難点です。また、IT人材の高齢化にともない、古い技術やシステムの全体像を把握する技術者が減少傾向にあり不足すると懸念されており、安全性の観点でも多くのリスクが存在します。これらの背景から、日本経済にも少なからず影響を与えると予測されています。そのため、金融業界ではDXによるレガシーシステムからの脱却が必要不可欠とされているのです。
金融DXの具体的な取り組み事例
経済産業省では、企業の戦略的なIT利活用を促す支援の一環として「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」の選定を行っています。DX銘柄では、DX推進に取り組む企業を認定するとともに、ビジネスの成長や競争力強化を実現したモデルケースとして情報発信しています。
こちらでご紹介する企業の取り組みは、2022年度のDX銘柄に選定された、金融業界の企業の活用事例です。金融DXの成功事例として、ぜひ参考にお読みください。
【出典】「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2022」(経済産業省)
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
株式会社ふくおかフィナンシャルグループは、日本初のデジタルバンクとなる「みんなの銀行」を設立しました。次世代型の金融サービスであるデジタルバンクは、全ての銀行業務をスマートフォン上で完結できるのが大きな特徴です。システムは従来の銀行サービスの概念にとらわれない発想により、ゼロベースで設計されています。たとえば、目的別に預金を仕分けできる「ボックス」、タッチ決済でもオンラインでも使える「バーチャルデビットカード」など、これまでにない金融機能が搭載されています。
デジタルバンク「みんなの銀行」の設立により、同社はデジタル時代のニーズに適した銀行サービスを創出し、金融業界のビジネスに新たな価値を生み出しました。今後は、デジタルバンクの機能をパートナー企業に提供することで、「Banking as a service(BaaS)」事業が本格的に展開されます。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の経営戦略では、次世代型の証券ビジネスとして「証券DX3.0」を目指すとともに、次世代向け金融サービスツールの拡充が進められています。同社はDXプラットフォームの機能を有するビジネスモデル「東海東京デジタルワールド」の取り組みで、経済と社会に貢献する新しいサービスを提供しています。
ビジネスモデルの主な特徴となっているのは、「FinTech機能の融合による新しいサービス」「地方創生」「パートナーとの連携」などのポイントです。先進性のあるFinTech機能を活用しながら、地域金融機関や地方自治体と協業することで、これまでにない新しいサービスの提供が可能となりました。地方銀行との提携や自治体への機能提供により、地域経済に大きく貢献しています。また、協業パートナーと連携してサービスを提供し合い、デジタル金融のエコシステムを構築する取り組みにも注目です。
東京センチュリー株式会社
リース・ファイナンス事業を行う東京センチュリー株式会社は、「金融×サービス×事業」を融合させたビジネスモデルを展開しています。「サブスクリプション・DX共創モデル」は、同社の金融サービス機能の事業基盤をSaaSで提供することで、パートナーとの共創に活用するのが特徴です。協業プロジェクトでは、パートナー企業の価値向上に貢献すると同時に、同社のリース・ファイナンス事業の価値向上にもつながっています。
たとえば、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社との協業プロジェクトでは、同社が金融サービス機能やサブスクリプション統合プラットフォームを提供。これにより、脱炭素社会に貢献する太陽光発電向けパワーコンディショナの定額貸出サービスが新たに創出されました。
金融DXを推進するためのポイント
最後に、金融企業がDXを推進するにあたり、押さえておきたいポイントをご紹介します。以下のポイントを参考に金融DXの施策を実施しましょう。
明確なビジョンの設定
金融DXの施策では、初めに自社のビジョンや目標を明確化することが大切です。現状のビジネスの見直しを行い、今後どのように刷新していく必要性があるか、方向性を定めましょう。その際は、単に電子化するのではなく、顧客や社会に対してどのような価値提供ができるかを示す必要があります。
戦略の策定
長期的な視点でDX推進の計画を立て、段階的に実行するためのロードマップを作成すると良いでしょう。戦略策定においては、マーケティングの観点から調査を実施し、顧客ニーズに即したビジネスを創出することが重要です。また、戦略を推進するための組織体制を整備し、全社的に取り組める環境を作りましょう。
デジタル人材の確保
DX推進にはエンジニアやデータサイエンティストをはじめとしたデジタル人材が必要です。自社の従業員をスキルアップさせるか、あるいは採用・外部委託などの方法での確保を検討しましょう。
従業員をスキルアップさせる場合は、トレーニングの機会を提供します。人材育成によってITリテラシーへの理解を深め、スキルを向上させることで、社内でシステム開発やデータ利活用を実現できるようになります。一方、既存の従業員のみで対応が難しい場合は、採用や外部委託によって専門知識を有する人材を社外から確保するのも一つの手です。
自社業務に適したツールの選定
DX推進の一環でツールを導入する場合は、自社の業務に適したサービスを選定しましょう。その際は、オンプレミス・クラウドシステムなどの導入形態、搭載されている機能、価格帯などを比較検討します。ツールへの投資では、コスト面のみでなく、ビジネスにもたらすメリットまで考慮するのがポイントです。たとえば、導入・運用で一定の費用がかかるとしても、ペーパーレス化やリモートワークの実現により結果としてコストメリットが期待できるケースもあります。
セキュリティの強化
DX推進の施策ではサイバー攻撃のリスクに備えてセキュリティ対策の強化に取り組みましょう。ツールを導入する際は、ベンダーが提供するセキュリティ対策の内容を確認しておくと安心です。アクセス制限、不正アクセスの検知、データの暗号化、パスワード認証などの仕組みによって、あらゆるセキュリティ上のリスクに備えておく必要があります。特に、金融業界では重要なデータを扱うことから、セキュリティの堅牢性を重視しましょう。
金融DXの導入でビジネスの優位性を確保しましょう
ここまで金融業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)について解説しました。DXとは、デジタル技術を用いた業務の変革を指す用語です。金融業界ではレガシーシステムへの依存などの問題を受けて、各社がDX推進へ取り組み始めています。DXの施策によって、金融業務の効率化、金融サービスの安全性向上および高度化といったメリットが期待されています。自社のサービスや業務プロセスへDXを取り入れ、ビジネスの成長や競争力強化につなげ、優位性を確保しましょう。
電話放送局(DHK)では、企業の電話業務を自動化する各種ソリューションを提供しております。金融業界の企業様にもご活用いただき、DXにおける施策の一環として業務効率化にお役立ていただいています。なかでも金融サービスと相性が良いのは、自動音声を用いたダイレクトメッセージのソリューション「オートコールIVR」です。こちらのソリューションの導入により、入金コールや書類返送依頼など、アウトバウンドの電話業務を自動化できます。
「オートコールIVR」では、自動音声応答(IVR)の技術を活用し、お客様へお伝えしたい内容を声でお届けできるのが特長です。たとえば入金コールの業務へ導入すると、IVRが自動でお支払い確認のご連絡を行うため、オペレーターから電話をかける必要がありません。機械による案内は、オペレーターが案内する場合と比較してトラブルや苦情を軽減できるのもメリットです。大量回線による一斉架電が可能なため、これまでのDMやメールに代わる販促手段としてもご利用いただいています。
金融DXで電話業務の改善を検討される際は、どうぞお気軽にDHKへお問い合わせください。
オートコールIVR
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、ボイスボット・IVRを活用した電話業務を自動化する手法や、ボイスボット・IVR提供会社を選ぶポイントを知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・コールセンターの電話業務をどこまで自動化できるのか知りたい
・自動化に適したコール内容を知りたい
・ボイスボット、IVR導入により、自動化に成功した事例を知りたい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(3)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711