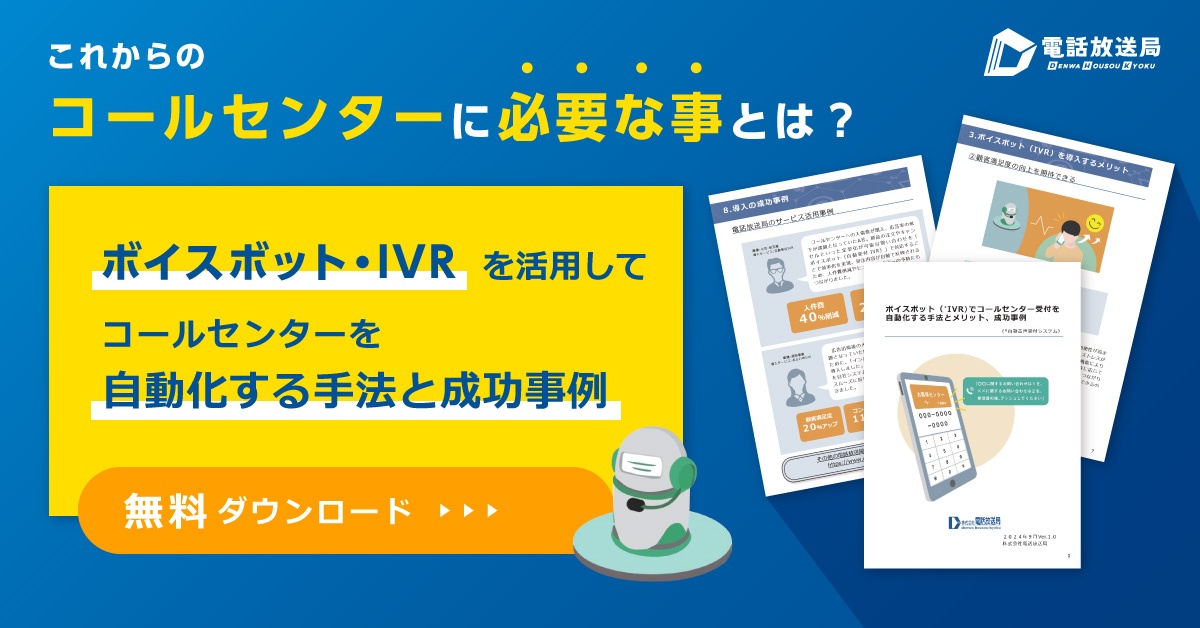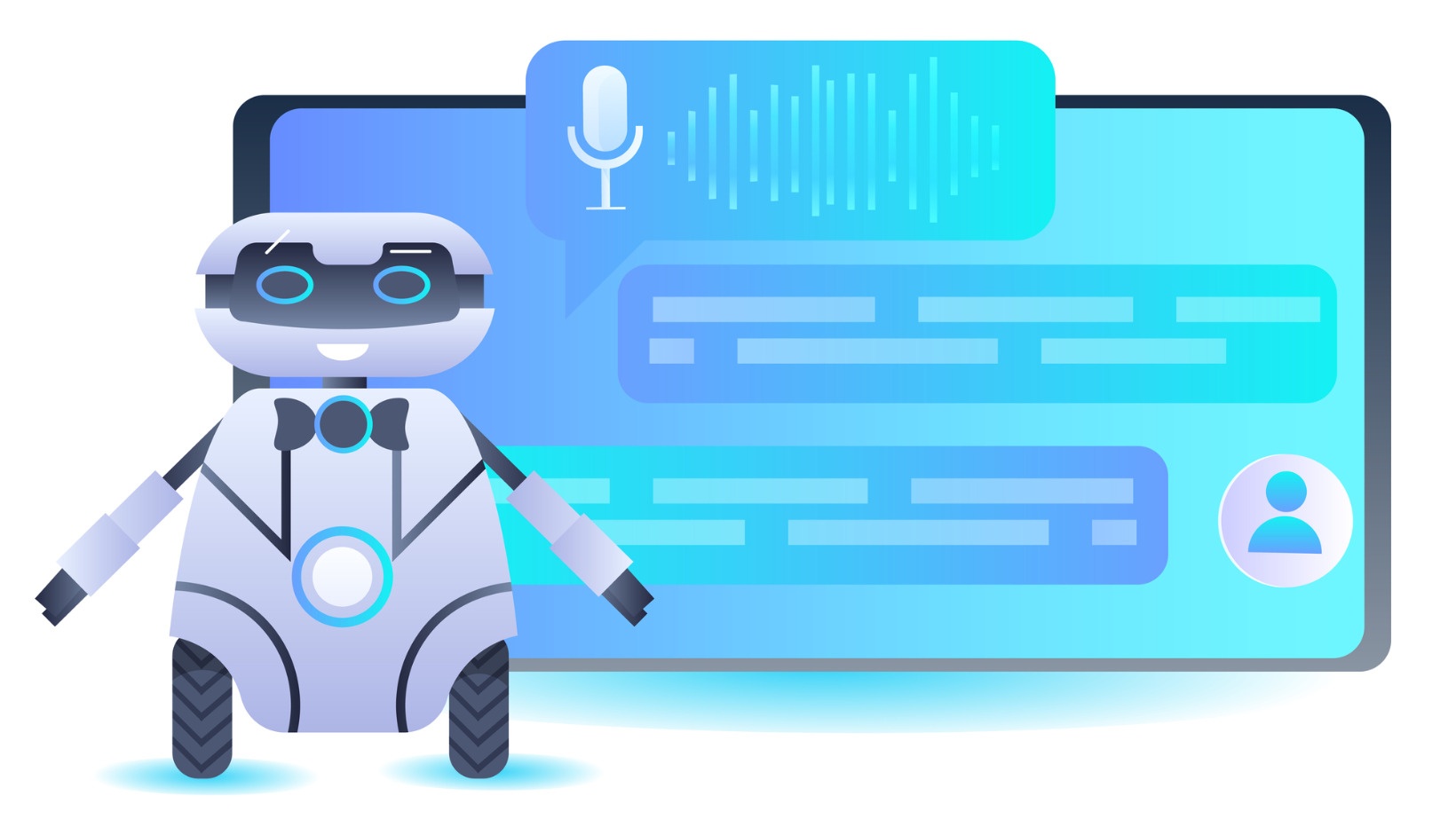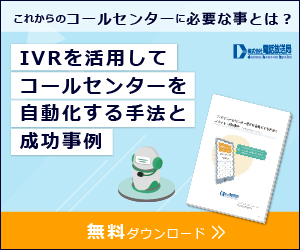ETOCとは?電話事業者認証機構の役割と重要性、認証のメリット
2025/02/04

近年の通信業界ではビジネス課題を解決する便利な電話サービスが登場している反面、電話を悪用した特殊詐欺などの不正の事例が多くなっています。自社に電話サービスを導入するにあたり、信頼できる電話事業者を見極める方法を知りたい企業のご担当者様も多いのではないでしょうか。
こうした背景から、2024年10月1日に「ETOC(電話事業者認証機構)」が設立されました。本記事では、ETOCの組織や認証制度について解説します。安全性の高い電話事業者を探す上で、ぜひ参考にしてみてください。
目次
・電話事業者やサービスの選定でETOC認証を参考にしましょう
ETOCとは何か?

初めに、通信業界で設立された認証団体「ETOC」に関する基礎知識を解説します。ETOCの設立の背景や目的をご紹介します。
ETOC設立の背景
ETOCとは、2024年10月1日に日本の電気通信事業者団体によって設立された、非営利の組織です。電話事業者認証機構(=Elite Telecom Operator Certification body)を略してETOCと呼ばれます。以下の5つの事業者団体がETOCを設立し、運営を行っています。
・一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)
・一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)
・一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)
・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(JCTA)
・一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会(JUSA)
ETOCが設立された背景として、電話や通信を用いた特殊詐欺による被害の増加が挙げられます。具体的には、なりすましにより金銭をだまし取る「オレオレ詐欺」、恋愛感情や親近感を悪用して金銭をだまし取る「ロマンス詐欺」などが代表例です。警察による取り締まりが実施されているものの、特殊詐欺の認知件数や被害総額は依然として増加傾向にあります。その要因の一つとして、悪質な利用者に電話サービスを提供する電話事業者の存在が挙げられます。
そこで、2023年に総務省が有識者による検討を実施したところ、電話事業者の適格性を評価する外部機関による信用確認が有効だと結論づけられました。ETOCはこうした結論を踏まえて設立され、通信業界のサービス品質向上や電話市場の健全化に取り組んでいます。
ETOCの目的
ETOCの目的は、電話事業の健全な発展と消費者保護です。特殊詐欺による被害が懸念される通信業界において、信頼性と透明性の高い電話サービスの提供を目指しています。
昨今の特殊詐欺の被害拡大には、悪質な利用者に電話サービスを提供する電話事業者が関わってしまっている状況です。そのため、業界内で連携して事業者の認証を行ったり、特殊詐欺の周知啓発活動に取り組んだりすることで、電話サービスの安心安全を推進する必要性があると考えられています。
ETOCの役割と活動内容

ETOCにはどのような役割があり、具体的にどんな活動に取り組んでいるのでしょうか。ここではETOCの組織の取り組みについてご紹介します。
ETOCの役割
ETOCでは、電話事業者に対する認証を実施するとともに、合格した場合に認証マークの発行を行います。外部機関であるETOCが事業者の適格性を評価することにより、一般の企業や消費者が事業者の品質を客観的に判断できるようにする役割があります。
通信サービスを利用する際、ETOC認証を信用確認に用いれば、不適正な事業者との電話番号や電話回線の取引を防ぐことが可能です。一般の企業や消費者が信頼性の高い事業者を選択できるようになることで、結果として特殊詐欺の防止に役立ちます。
ETOCの活動内容
ETOCでは認証を行うにあたり、善良な電話事業者を評価する基準を制定しています。具体的には「ネットワーク品質」「セキュリティ」「サービス品質」「個人情報保護」「社会的信頼性・防犯」「消費者保護」などの分野で複数の評価基準が設けられています。これらの基準を満たす日本国内の事業者に対して認証マークを付与する仕組みです。
認証を受けた事業者は、一般の企業や消費者との取引や契約において、認証マークを利用できます。利用者が電話サービスを選ぶ際、認証マークを参考にすることで信頼できる事業者を容易に見極められます。また、利用者への周知啓発もETOCの大切な活動内容の一つです。電話サービスの購入時に認証マークの確認を促すことによって、電話番号の適正利用を推進します。
万が一、認証を受けた事業者に不適正利用などの行為が見られた場合、ETOCにより速やかに評価の取り消しが行われ、認証は失効となります。また、認証取得事業者への情報の周知が行われることにより、認証の安全性が保たれます。
ETOC認証のメリット

企業が信頼できる電話事業者を見極める際、ETOC認証を一つの判断基準として参考にできます。ここでは、ETOC認証が社会にもたらすメリットを解説します。
電話事業者にとってのメリット
ETOC認証を受ける電話事業者は、認証マークの活用によって信用度が向上し、市場での認知度や信頼性を高められます。一般の企業や消費者からの信頼を得やすくなるのが大きなメリットです。
前述したように、ETOC認証には通信業界における信頼性のあるサービス提供を証明する仕組みがあります。事業者が認証マークを活用すると、利用者に安全性の高さをアピールして、ブランド価値を向上させることが可能です。市場での競争力が強化され、新規顧客の獲得が期待できるでしょう。
企業や消費者にとってのメリット
・安全で信頼できる電話サービスの選択
一般の企業や消費者は、ETOC認証に着目して電話事業者を選ぶことで、高品質な電話サービスを利用できます。ETOC認証を受けた事業者は、顧客対応窓口の設置やトラブル発生時の迅速な対応など、サービス品質に関して一定の基準を満たしているためです。
・特殊詐欺防止と消費者保護
ETOC認証を受けた事業者は、犯罪利用防止対策を講じています。本人確認の実施や疑わしい取引の防止などの基準を満たしているので、特殊詐欺に関わる事業者が排除される点で安心です。また、認証では一般の企業や消費者の保護を強化する基準も設けられています。
・安心安全な通信環境を構築
ETOC認証では、ネットワークやセキュリティの基準も評価対象となります。事業者は安全な通信環境を確保し、セキュリティの脆弱性に備えて対策を実施しています。そのため、一般の企業や消費者がセキュアで安定した電話サービスを利用できるのがメリットです。
電話事業者やサービスの選定でETOC認証を参考にしましょう
ここまで、「ETOC(電話事業者認証機構)」に関する基礎知識や、一般の企業や消費者にもたらされるメリットについてご紹介しました。ETOCは通信業界の事業者団体が連携して設立・運営し、電話事業者の認証や、認証マークの発行などを行っています。
ビジネスシーンで電話サービスを導入する場面では、信頼できる事業者の見極めが難しいことがあるでしょう。その際は、ETOC認証マークの有無をチェックすることで、優良な事業者を客観的に評価しやすくなります。電話サービスの導入を検討している企業のご担当者様は、ETOC認証マークを一つの判断基準とすると良いでしょう。
ETOCでは、2024年11月に「ETOC 第1回審査」の事前申込が開始されました。ボイスボット・I VR(自動音声応答システム)の各種サービスを提供する電話放送局は、ETOC認証を取得済みです。
ETOC認証登録事業者
これからも企業様に安心してご利用いただける電話サービスを提供するために取り組んでまいります。電話業務の課題解決はぜひ電話放送局へご相談ください。
DHK CANVAS
お役立ち資料 無料ダウンロード
本資料では、ボイスボット・IVRを活用した電話業務を自動化する手法や、ボイスボット・IVR提供会社を選ぶポイントを知ることができます。
【本資料は、下記の関心をお持ちの方におすすめです】
・コールセンターの電話業務をどこまで自動化できるのか知りたい
・自動化に適したコール内容を知りたい
・ボイスボット、IVR導入により、自動化に成功した事例を知りたい
関連コラム
おすすめコラム
IVRをご検討中の方
簡単・便利なIVRを体験
カテゴリー
- ACD(2)
- AHT(1)
- AIエージェント(3)
- BPO(4)
- CPaaS(2)
- CS調査(6)
- CX(3)
- DX(11)
- EX(1)
- FAXDM(1)
- KPI(4)
- PBX(3)
- PCI DSS(2)
- RPA(1)
- SMS(2)
- SMS送信IVR(3)
- VOC(7)
- あふれ呼(5)
- アンケート(5)
- インバウンド(2)
- オートコール(8)
- カスハラ(7)
- カード決済(3)
- キャンペーン活用(1)
- コンビニ決済(1)
- コールセンターシステム(8)
- コールフロー(4)
- コールリーズン(5)
- チャットボット(2)
- テレワーク(2)
- バックオフィス(8)
- ビジュアルIVR(1)
- ボイスフィッシング(1)
- ボイスボット(8)
- ボイスボット・IVR選び方(15)
- マニュアル(11)
- 基本(1)
- 多要素認証(4)
- 多言語(1)
- 生成AI(3)
- 用件振分・情報案内(5)
- 督促(4)
- 自動受付IVR(1)
- 自治体DX(5)
- 電話取り次ぎ(14)
- 電話認証(4)
IVRで電話業務を自動化する手法や、IVRサービス提供会社を選ぶポイントを知ることができる資料を無料提供
IVRで課題解決
こんな課題ありませんか?
- 電話対応を自動化したい
- あふれ呼や営業時間外の機会損失を減らしたい
- 災害時のBCP(事業継続計画)やテレワークに活用したい
お電話からのお問い合わせ
-
大阪(西日本エリア)
06-6313-8000 -
東京(東日本エリア)
03-3645-1711